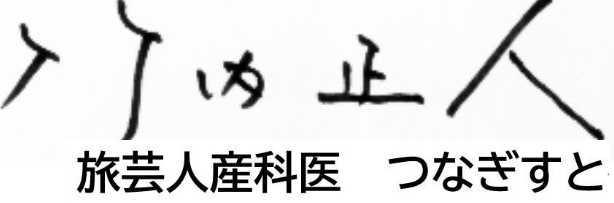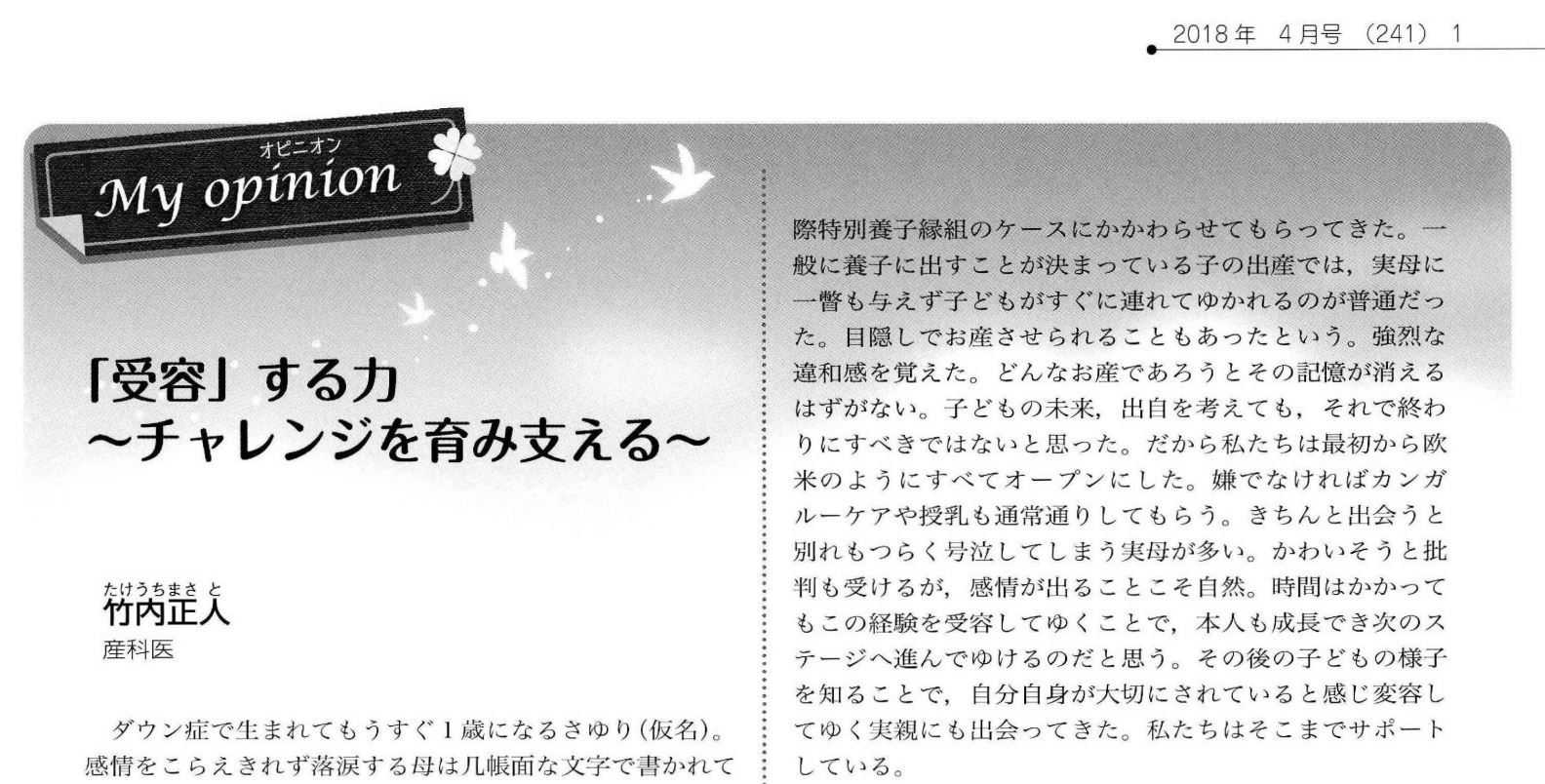NOTE ノート
「受容」する力~チャレンジを育み育てる~
チャイルドヘルス Vol21 No4 2018
ダウン症で生まれてもうすぐ1歳になるさゆり(仮名)。感情をこらえきれず落涙する母は几帳面な文字で書かれている育児記録を見返していた。中くらいの段ボールには、きちんと整理されたアルバム、丁寧に畳まれた可愛い洋服とおもちゃが詰められている。「私たちが亡くなった後のことを考えると、どうしても育てることができなくて・・」、申し訳なさそうに母が告げると、終始無言であった父に抱っこされていたさゆりは、アメリカ人の養父母へ手渡された。「あなたたちの大切なお子さんを私たちが大切に育ててゆきます。さゆりを産んでくれてありがとう」、養母は実母をあたたかくハグをした。
それから2年、その養父母家族はもうひとりダウン症の男の子を迎えてくれることになった。今回は、実子である中学生の姉と小学生の兄、そして3歳になったさゆりも一緒だった。さゆりを見て驚いた。当たり前と言えば当たり前なのだが、表情としぐさがすっかりアメリカ人になっていたからだ。さゆりのお世話を姉が、今回迎えてくれる男の子を兄がごくごく自然にあやしている様子にも心動かされた。先に「上にふたりのお子さんがいるのに、どうしてふたりも・・」と陳腐な質問をしてしまった自分が恥ずかしかった。養父母は「ひとりよりふたりの方が、お互いにいい影響を与え合えるから」と、話してくれた。文化、宗教、コミュニティーなど背景は違うが、家族全体から放たれていた「受容」する力(オーラ)が、さゆりを包みこみ育んでくれたんだろうと感じとれた。
産科医である私は、特別養子縁組あっせん団体「アクロスジャパン」の顧問として、これまで多くの国内及び国際特別養子縁組のケースにかかわらせてもらってきた。一般に養子に出すことが決まっている子の出産では、実母に一瞥も与えず子どもが直ぐに連れてゆかれるのが普通だった。目隠しでお産させられることもあったという。強烈な違和感を覚えた。どんなお産であろうとその記憶が消えるはずがない。子どもの未来、出自を考えても、それで終わりにすべきてはないと思った。だから私たちは最初から欧米のようにすべてオープンにした。嫌でなければカンガルーケアや授乳も通常通りしてもらう。きちんと出会うと別れも辛く号泣してしまう実母が多い。可哀そうと批判も受けるが、感情が出ることこそ自然。時間はかかってもこの経験を受容してゆくことで、本人も成長でき次のステージへ進んでゆけるのだと思う。その後の子どもの様子を知ることで、自分自身が大切にされていると感じ変容してゆく実親にも出会ってきた。私たちはそこまでサポートしている。
長年の慣習の前に思考停止し疑問にさえ思わなくなっていた「なかったこと」にする文化への私のチャレンジは20年以上前に遡る。産科医になって10年、命を救い助けると頑張ってきたが、母子や家族が幸せになっているとは思えず、産科医を続ける意味がわからなくなっていた頃に手探りで始めた流死産のグリーフケアだ。当時、死産となった子どもは「人」でなく「モノ」として取り扱われ母と会えることはなかった。なくなった子どもを「人」として丁寧に扱うことで家族の感情が表出し、しっかりと出会える環境が育まれていった。こうした産科医の経験から「受容」は、その時点では辛いが、物語を紡ぎ、子どもだけなく、親、すべての人=社会を育み変容する力になることを学んだ。
2019年4月末で平成が終わる。概ね平和な時代であったが、経済・外交の停滞のほか、日本人の生き抜く力が危惧される様々な徴候が顕在化し、日本の衰退をつきつけられた時代でもあった。目の前の問題に向き合えず、根本的な解決を先送りしてきたつけともいえるだろう。テクノロジーの加速度的な進化もあり、予測できない期待もあるが不安が大きな次の時代を生きてゆく子どもたちは、思考停止ならず、自分で考え俯瞰し、決断と行動ができる大人に育ってほしいと切に願っている。そんな子どもたちのチャレンジを育み支えるキーワードこそこの「受容」する力だと思う。