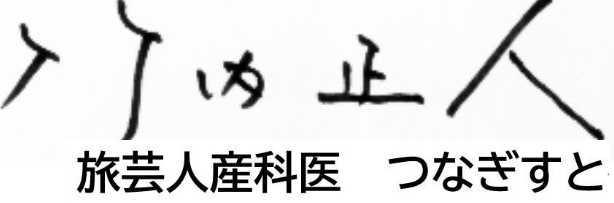NOTE ノート
平成27年度 大東文化大学文学部教育学科 秋季定例会
「今生きていること ~命って当たり前ではない~」
平成27年10月23日
- 前半 -
【竹内】皆さん、こんにちは。産科医の竹内正人です。今日は貴重な機会をいただきありがとうございます。今回、担当の学生が私のホームページを見てくれたのがきっかけだそうですが、最初に連絡をもらったときは文系の大学生から?って、また担当の方が「子どもの死」とか「誕生死」に関心があると知って驚きました。産婦人科には産科と婦人科がありますが、僕の専門は産科です。今でも月に10日は当直をしています。昨夜も当直で…深夜に2人お産があって、今朝もひとり産まれました。午前中、こちらに来させてもらう前は外来で妊婦さん30人ほど診てきました。そうした命に寄り添う日のなかで、自分が感じたことを、何らかの形にしてゆければなと思いながら日々を過ごしてきました。よくひとりで考えたり、かなり突飛のないことを妄想したりもしています(笑)。今回、スタッフでも男子学生が最初に見つけてくれたと聞きましたが、定例会の講演を決めるとき、よく僕にたどりついたなと思いました。女子学生であれば、もし僕にたどり着いても、誕生死からでなく、これも僕の仕事の「ルナルナ」からだったかもしれませんね。
今回のサブタイトルに「周産期の死」という言葉を使っていますが、「周産期」は専門的な用語なので簡単に説明しておきますね。「周」というのは、周辺の周です。「産」はお産です。つまり周産期とはお産前後の時期のことです。「周産期の死」、お産の時期の死というと、産まれてきた子が病気で亡くなる印象かもしれませんが、それだけではなく、たとえばお腹の中で赤ちゃんが亡くなることがあれば、産まれてすぐに亡くなることもあります。流産があれば、死産もあります。亡くなりかたも、お腹の中で生を全うした死もあれば、望まれない妊娠での中絶もありますよね。それも周産期の死です。また、子どもだけではなく、お母さんの死もあります。日本ではお母さんが死ぬというイメージはあまりないかもしれませんが、人が人であるかぎり、どれだけ医学や科学が発展しても、お母さんの死を含めた周産期の死がなくなることはありません。ただ、お母さんが亡くなることは少ないので、お母さんが亡くなると「医療事故?」のように思われてしまうかもしれませんね。人間はミスをするので、医療ミスと言われる事故も、もちろんあります。いずれにしても、人は死ぬんです・・・。ただ、産科医になるときには、僕には産科で死と向き合う意識はありませんでした・・・。おめでとうといえる唯一幸せな科という普通のイメージだったし、医師になるということは「救う」「助ける」がメインだったからです。皆さんのなかの多くの方が教員になるのでしょうが、学生から教師になっていくプロセスがあるように、僕にも医学生から医者になっていくプロセスがありました。そのなかで、死に対してどう自分が向き合うのか、そういうことを十分に考える時間がなかったのでしょう。これは大きな欠落でした。
僕が大学を卒業したのは昭和62年、1987年で、早いものでもう30年くらい経ってしまいました。学生の頃はバックパッカーとして、海外を放浪したりしていました。放浪をしながら、将来はアフリカへ行って貧しい子どもたちを救えたらいいなみたいなことを漠然と考えていました。日本でも貧困や、格差が問題になっていますが、放浪しながら、どの国の、どんな地域の、どんな家庭に生まれたかによって子どもの人生は大きく違ってくるんだなと感じていました。僕は、平和な日本に生まれて、いろいろな縁や恩恵を授かって、こうして生きてるんだとな思ったんです。
その前に、私たちがこの世に生まれてきたこと自体の確率が天文学的なんです。具体的に、卵子ですが、皆さんは20歳くらいでしょうが、その頃の女子に残っている卵子は、20~30万個ぐらいです。残っているというのは、お母さんのお腹の中にいたときには600万個もあったからです。それが、産まれた時にはすでに100~200万個に減りました。そして初潮をむかえた頃は30万個くらいになって今に至ってるんです。これからまた時がたち、30歳になると10万、40になると1万とだんだん減っていきます。ただ、卵が毎月排卵されたとしても、女性が生涯で排卵する卵は500個くらいしかありません。あとの卵子は排卵することもなく自然に消滅してゆきます。そのひとつの卵子と、ひとつの精子が受精します。精子が少ない男性もかなりいることがわかっていますが、1ccの精液にいる精子は正常だと5千万にもなるんです。だから5ccの精液であればそこには2億5千万もの精子が生きています。5ccに2億以上って凄くないですか?そのなかの、そして、そのときの精子の1人というかひとつが、もともとは700万あったうちの、その時に排卵したひとつの卵子と受精して、その受精卵が子宮に着床して育っていくと赤ちゃんになるんです。命の源を辿っていくと、この世に自分がこうして生きているって・・とんでもないことなんです。あともう一つ、とても不思議なのは、そうして受精した受精卵が成長して自分のカラダができていくんですが、そのカラダの中にどうして私がいるのかということです。カラダとココロはセットのように思うかもしれませんがやっぱり別ものなのでしょう。LGBT(※レズビアン[女性同性愛者]、ゲイ[男性同性愛者]、バイセクシュアル[両性愛者]、トランスジェンダー[心と体の性が一致しない人]の方々のこと)を考えてみても、カラダは男性だけどココロが女性だったり、その逆だったり。そうしたことが普通にあるんです。(※20人に1人はLGBTという説もあります)自分のカラダにどうして私が宿っているのかは説明がつきません。もし自分の基になった卵子が実際に受精した精子でなく、その隣の精子と受精してたらどうなってたんだろう。同じ両親から産まれた兄弟は似ていてもカラダとココロが違うように、もし卵子は同じでも隣の精子と受精していたらカラダは少し違ったにしても、ココロも違ったんだろうか?そのカラダに今の自分はいたんだろうかって・・・。生殖のしくみを知ってから、よくそんなことをよく考えていました。
話しがそれましたが、僕は1961年の比較的豊かで平和な時代の日本に生まれました。僕らの世代は、無気力とか無関心世代と言われもした。そうした時代に育ち、僕は医学生になり途上国を放浪しながら、自分が育った世界とは違う文化や民族と出会い、自分って何者なんだろうとアイデンティティを模索していたんだと思います。貧しい途上国を歩いていて、もし自分がここで生まれていたら、どう生きて、何をしていたんだろう・・。そんなこともよく考えていました。アフリカでは子どもたちもそうですが、多くのお母さんもお産で命を落としていることも知りました。世界では1日1500人の妊婦がお産で命を落としているといわれていますが、その多くがアフリカでもサブサハラといってサハラ砂漠の南側の地域です。ひとつのたとえですが、毎日全員が妊娠している女性が乗った250人乗りのジェット機が4時間ごとに6機墜落し、全員が亡くなっています。しかも、多くの機体がサブサハラに墜落しています。日本ではお産が100万あればそのうちの100人、それでも日本でも1万人に1人のお母さんがお産で亡くなるんです。ところがサブサハラやアフガニスタンでは1万人にたぶん400人くらい亡くなっている。産まれた地域によって全然違ってくる。こういう状況を知って、日本で産まれた僕に何ができるんだろう・・? 子どももそうだけど、その子どもを産むお母さんを救えないのだろうか・・・って考える自分がいました。じゃあ小児科じゃなくて、産婦人科・・・。う~ん、産婦人科は、女性だけしか見れないし・・ と制約される感じがしたのと、テレビドラマ、白い巨塔の影響か悪徳のイメージがあったので、抵抗がありました。でも脳外科、麻酔科、心臓外科とか、カッコいいなと思った科で自分が活躍する姿もイメージできなかったんです。当時は人気があって、希望者が多くいたことも自分がその道へ進む意味があるんだろうか?って思いました。産婦人科は人気がなかったことも大きな決め手になりました。どの科に進むのか本当に悩んだけど、最後はもうえい、っていう感じで進路を決めました。
産婦人科に進んでみると、入局前からわかっていたころですが、病院に泊りこみで家には帰れないし、何もせずただただ待っている時間がとても長かったんです。これはストレスでした。しかも給料は4万円くらい。6年大学へ行って医者になっても、家には帰れないし、自活もできない。当時の医師ってそんなものでしたが、明らかにブラックですよね。こんなのやってられないよって、辞めようとも思ったんですけど、でも「1年で辞めてしまうってどうなの」とも考え、考え直して、もうちょっと頑張ってみようかと。
働く環境はよくなかったんですけど、当時はテクノロジーが医療現場にどんどん入ってきて、学問としての産婦人科は面白かった。最新の技術と、知識を身につけて、まずは日本でお産をする子どもとお母さんは全員助けるんだ…みたいな。無理な話しなんですけど、当時は本気でそう思っていました。1990年代に入ったころですが、日本の赤ちゃんは千人のうちもう3人しか死なない時代でした。千人で3人も死ぬともいえるんですが。それがアフガニスタンでは千人で165人も亡くなっていた。医療がなくて、何もしなくたって、そんなに亡くなるはずはないだろうというのが現場に出て感じた感想です。逆に何か間違ったことをしているんじゃないか。たとえば陣痛促進剤の濫用で子宮が破裂したり、自然に待てばいいのに無理に赤ちゃんを娩出しようしたり。中途半端な西洋医学が入ってきたばかりに、かえってお産が危険になっているんじゃないかと感じました。
そんな途上国から日本へ帰ってくると、いつも感じることがありました。途上国は暮らし向きがよくないだけでなく、平和でなかったり、政治も安定してなかったり、しかも、お母さんと子どもはたくさん死んでいる。それでも、人々の目、とくに子どもたちの目がキラキラと輝いているんです。生き生きしている感じがストレートに伝わってくるんです。ところが、日本に帰ってくると、ほっとはするんですが、平和でそれなりに豊かなのに、目の輝きを感じないんです。人や社会に生気が少ないというか、多くの人が抜け殻になってるんじゃないかってさえ感じてしまう。それってどうなんだろうと。
僕が訪れた途上国では、貧困の中を生き抜いていかなければという逞しさが逆に目の輝きになっていたのかもしれない。 そうした地域では年金や保険や生活保護などの社会保障は期待できないし、社会のセーフティーネットも、まずないんです。昔の日本もそうだったのでしょう。それが当たり前の環境だった。国に期待できないから、助け合いながらでも生き抜いて行くしかなかった。何もないなかから切り拓いて行こう…みたいな力が輝きとして映ったんだろうと思いました。僕もそうですが、ものがあって当たり前のなかで生まれ、育ってきました。社会から守られることは権利で、それが不十分だと不平・不満ばかりで、自分で切り開いていこうとエネルギーが生まれにくい社会になっている。普通に考えれば、国にこれだけ借金があって、少子で年々人口減少が進んでいくのに、生き抜く力が育まれなければ、いずれ国は破綻してゆくって想像できるはずです。今は未来を食いつぶして、問題を先送りしているだけ。昔は5人の労働者で1人の老人を支えていたのに、それが3人、2人、1人となってゆく。そんなの無理だし、昔のつけをなぜ自分たちが払わなければいけないの?年金だって…どうせ払ったって、自分たちはもらえないんだから払うだけ損とか。言い分は理解できるけど、事実としてもうここまで来てしまっている。この時代にこの国に生まれたものとして、「自分1人で十人…いや百人ぐらい養おう!」みたいな元気な人たちが増えてくればってこと思うんだけど、どうすれば、そうした気運が生まれてくるのか・・・。
そうした地域では年金や保険や生活保護などの社会保障は期待できないし、社会のセーフティーネットも、まずないんです。昔の日本もそうだったのでしょう。それが当たり前の環境だった。国に期待できないから、助け合いながらでも生き抜いて行くしかなかった。何もないなかから切り拓いて行こう…みたいな力が輝きとして映ったんだろうと思いました。僕もそうですが、ものがあって当たり前のなかで生まれ、育ってきました。社会から守られることは権利で、それが不十分だと不平・不満ばかりで、自分で切り開いていこうとエネルギーが生まれにくい社会になっている。普通に考えれば、国にこれだけ借金があって、少子で年々人口減少が進んでいくのに、生き抜く力が育まれなければ、いずれ国は破綻してゆくって想像できるはずです。今は未来を食いつぶして、問題を先送りしているだけ。昔は5人の労働者で1人の老人を支えていたのに、それが3人、2人、1人となってゆく。そんなの無理だし、昔のつけをなぜ自分たちが払わなければいけないの?年金だって…どうせ払ったって、自分たちはもらえないんだから払うだけ損とか。言い分は理解できるけど、事実としてもうここまで来てしまっている。この時代にこの国に生まれたものとして、「自分1人で十人…いや百人ぐらい養おう!」みたいな元気な人たちが増えてくればってこと思うんだけど、どうすれば、そうした気運が生まれてくるのか・・・。
先ほど、一つ前のスライドにもありましたように、日本では千人のうち3人なのに、ある国は千人のうちに165人もの赤ちゃんが周産期に亡くなっています。乱暴な言い方かもしれませんが、それでも800人以上は生きるんです。じゃあ、お産を生き抜いた命がその後どう生きていくのだろうということはこの表からはわかりません。産科医である僕が関わっていたのは、あくまでも「救う」「助ける」という表面的なところだけで、その反映は統計数値で表せます。でも、大切なことって、きっと数値では表せないんでしょうね。当時の僕は、生まれてきた子たちが、その後にどう生きてゆくのかにあまり関心がありませんでした。ところが、1990年当時のバブルがはじけた頃、社会がどんどん壊れていった。経済だけでなく、母子や家族の関係性が悪くなり、虐待がどんどん増えてゆき、逆に子どもが親を殺したり・・。
お産で死ぬ命が少なくなっても、その後の母子、家族、そして社会が幸せになってないじゃないか、と突きつけられたようでした。海外では絶対助からない、妊娠22週の400グラムの子どもが日本では助かりうるんです。400、500グラムって、こんなに小さいんですよ。それもインタクトサバイバルといって、障害もなく助かる命があるんです。それは素晴らしいことです。ところが、助かった命がその後に幸せに生きていくかはまた別問題です。障害なく助かっても、小さな命が助かるのと一緒に、それを受け入れる社会も一緒に育っていかなければ、家族の負担が増えるだけかもしれません。逆に生かされた命が家族崩壊の原因となってしまうこともでてくる。医師の仕事は命を助けることで、家族や社会がどうなるかまで責任はないのかもしれません。ここに関心がある医師はその頃は少なかった。当時の僕も、夜も寝ないで、日々こんなに一生懸命働いているのに、どうして社会はよくなっていかないんだって、いつも憤っていました。
こうして産科医として時間を重ねているうちに、多くの気づきがありました。この写真は「赤ちゃんの死を前にして」という本に掲載したもので、20年くらい前に撮らせてもらいました。これまで「救う」「助ける」できた僕が、救えなかった命に関心をもつようになっていった頃です。実はこの赤ちゃんは亡くなっています。そうは見えないでしょ・・・。死んでいるのに、どうしてお母さんはこんな穏やかな顔をして亡くなったわが子を抱いているのでしょう。ここで起こったことは「常位胎盤早期剥離」といって、赤ちゃんに酸素と栄養を与える胎盤が、まだ赤ちゃんが産まれていないうちに、突然子宮から剥がれてしまう緊急事態です。胎盤が剥がれると赤ちゃんには急に酸素がいかなくなります。大出血となりお母さんが亡くなる危険もでてきます。このお母さんは近くの病院から、当時僕が勤めていた周産期センターへ運ばれてきました。お母さんは見るからに苦しそうで、お腹が硬くなっていました。超音波をあてると赤ちゃんは動いてなくて、心拍も確認できませんでした。「胎盤早期剥離だ!でも、すぐに帝王切開すれば救えるかもしれない」と、そのまま手術室に直行して、麻酔をしてすぐにお腹を切りました。子宮を切開すると、子宮の中から、血がシュパーッと噴き出してきました。お腹の中が血の海になりました。血の海の中から僕はこの子を取り上げました。小児科の先生が一生懸命蘇生してくれました。でも、結果的にこの子を救うことができなかった・・。救えると思っていた僕は無力感に包まれました。お母さんの話から、この子は病院につく2時間前までは元気だったようです。蘇生台の上で寝ているその子は、今にも目を開けて泣き出しそうでした。酸素がなくて苦しかったろうに、とても穏やかで可愛くて優しそうで、神々しくさえ見えました。
2000年以前は全国的に、お母さんが亡くなった赤ちゃんと会うことはできませんでした。では、その赤ちゃんはどこにいたのかというと、流し場で、手術で摘出した臓器を乗せる緑の布の上に置かれていたのです。お腹の赤ちゃんは亡くなったらもう人ではなく、モノみたいに取り扱われていました。それまでお腹の中で生きていた赤ちゃんを人として扱わないことって、おかしいんじゃないかと僕は感じました。周産期の死を意識することがなかった産科医としての最初の10年が過ぎ、「救う」「助ける」だけの産科に折り合いをつけることができなくなった僕は、自分がこれまで切り捨ててきたことに目をむけるようになっていたのです。そのひとつが周産期の死でした。
そうした実践がその頃の日本にはなかったので、海外文献を読んで勉強をしました。文化が違うからなのか、納得できないこともありましたが、亡くなった赤ちゃんとお母さんのケアの必要性は伝わってきました。新鮮でした。2000年頃の日本のお産現場では、赤ちゃんが亡くなった原因の検討はしていましたが、原因がわかればそれで終わっていたからです。このケースだと妊娠高血圧で胎盤が剥がれて、赤ちゃんが亡くなったんだと。医学的にはそれで解決します。だけど、お母さんからは、どうしてそれが私に起こったの。どうして亡くなったのは私の子だっなの?医学の言葉ではそこは説明できないのです。私が悪かったの?どうすれば避けられたの?
医学的な解決と、お母さんの納得はまったくをもって違っていました。医学はそうしたことに長い間、配慮ができていませんでした、「胎盤剥離だったらしょうがない。お母さんが助かって何よりです」、「まだ若いから、今回はあきらめて、また次がんばりなさい」みたいな感じで、今回のことはなかったこととして、できるだけショックが残らないように幕引きをしようという感じです。お母さんが赤ちゃんと会わないことは、お父さんと家族も納得していて、その決断にお母さんの意向はまったく反映されませんでした。かつては赤ちゃんが亡くなって3日ぐらい経ってから事実を伝えることもありました。今はお母さんにすぐに伝えるようになっていますが、すぐに伝えると感情がでます。以前であれば、「あぁ、やっぱりすぐに告知すべきではなかった」となったかもしれません。ただ、これは有りなんです。日本で育ってくると、できるだけ感情を出さないとか、人に迷惑や心配をかけないとか・・・。でも、感情が出るというのはすごく自然で大切なことです。この写真は、助けることができなかった赤ちゃんを連れていって2時間ほどたった時の写真です。私の著書「赤ちゃんの死を」前にしてに、お母さんとご家族の許可を頂いて掲載させてもらった写真です。
最 初に、「救うことはできませんでした・・」と、温かいタオルにつつんだ赤ちゃんを連れていって、お母さんに手渡しました。赤ちゃんが元気で普通に産まれたときに、低体温にならないように温かいタオルで赤ちゃんを包みます。でも、亡くなった赤ちゃんには、医学的には温かいタオルは必要ないんです。実際、これまでは、水場の布の上に冷たくなって置かれていました。それをみんな何とも思わなくなっているんですよ。医療者になってはじめてその状況を目の当たりにすると、「えっ?」って思うでしょう。でも、そんなものなのかと、だんだんそれが普通になっていきます。こわいですよね。教員の世界でも、きっと同じようなことがあると思うんです。その業界では当たり前なことが世間では当たり前じゃないことがあります。普通は「えーっ!」と思うことも、おかしいと思わなくなるんです。でも、やっぱりこれはおかしい、と思い続けられることが大切です。僕も、医師になって水場に置かれた赤ちゃんを、おかしいと思えなくなっていました。それが10年たって、やっぱりこれっておかしいよって、また思えるようになった。
初に、「救うことはできませんでした・・」と、温かいタオルにつつんだ赤ちゃんを連れていって、お母さんに手渡しました。赤ちゃんが元気で普通に産まれたときに、低体温にならないように温かいタオルで赤ちゃんを包みます。でも、亡くなった赤ちゃんには、医学的には温かいタオルは必要ないんです。実際、これまでは、水場の布の上に冷たくなって置かれていました。それをみんな何とも思わなくなっているんですよ。医療者になってはじめてその状況を目の当たりにすると、「えっ?」って思うでしょう。でも、そんなものなのかと、だんだんそれが普通になっていきます。こわいですよね。教員の世界でも、きっと同じようなことがあると思うんです。その業界では当たり前なことが世間では当たり前じゃないことがあります。普通は「えーっ!」と思うことも、おかしいと思わなくなるんです。でも、やっぱりこれはおかしい、と思い続けられることが大切です。僕も、医師になって水場に置かれた赤ちゃんを、おかしいと思えなくなっていました。それが10年たって、やっぱりこれっておかしいよって、また思えるようになった。
この写真の赤ちゃんどうみてもかわいいじゃないですか。最初に蘇生台の上に横になっているこの子を見たとき、お母さんがこの子に会えないってどうなんだろうと感じました。これまでだと、お父さんに説明して、お母さんは会えずにそのまま葬儀場に運ばれて焼かれていたんです。お母さんに会えない理由は、お母さんがトラウマになるといけないから、とか忘れなれなくなるから…みたいな理由です。こうした根拠もない誤った認識が当たり前になってしまっていたんです。だって、モノじゃないんですよ。大切なわが子なんです。僕が勤めていた病院でもそうでした。でも、このとき初めて亡くなっている赤ちゃんを温かいタオルに包んで、水場でなく、お母さんのもとへ連れていったんです。その時、僕は産科部長だったんで、「どうして先生、そんなことをしているの?」みたいな…。周りは、それっておかしくないという雰囲気でした。でも、部長権限で勝手に慣習を破ってしまいました。お母さんは最初はギャーって、嘆き悲しんでいました、でもずっと抱っこして1時間くらい経つと、その表情がおだやかになっていったんです。直接触れることが大きいんです。触れるってすごく大切なことです。皆さん、触れるですよ。触れ合うって人間の原点なんです。人間には五感がありますよね。視覚・聴覚・嗅覚・味覚、そして一番の原点が皮膚感覚、触覚です。一番最初に獲得する感覚で、妊娠3ヶ月頃、まだ私たちが3~5cmくらいの時にはすでにもうあるんです。で、最初に触れられていたのが子宮です。子宮との触れ合いが人の原点なんです。イヤな人に触れられるとセクハラだけど、好きな人に触れられると落ち着くし、癒されます。日本は触れる文化が育たなかったから、生きづらいのかなとも思います。以前に17歳と49歳の男性の自殺率が高いって言われてました。そんな兆候は海外にないんですけどね。17歳と49歳というと誰からも触れられにくい時期なんです。心からハグをできる相手がいれば、だいぶ違うはずなんだけどな。そこが人間の原点です。赤ちゃんが産まれたら、「オギャー」と泣くと思うかもしれませんが、カンガルーケアといって、産まれてきた赤ちゃんをそのままお母さんが抱っこすると、赤ちゃんは安心して泣かないんです。元気だから「オギャー」だけど、不安でもあるんです。今までずっと子宮の中で包まれていたのに、急に外に出てきたんですからね。
また先ほどの写真にもどりますが、添い寝をすることで、子どもが亡くなってもお母さんになっていったんです。いいですか、子どもに会わせたらトラウマになると言われていましたが、亡くなっても自分の子です。やっぱり可愛いはずなんです。それまでは、つらいことは蓋をして忘れようでしたが、逆にこれがトラウマになる。逆境を乗り越えるということは忘れることではなく、その事実と折り合いをつけていくこと、共存していくことです。つらいことがあって、最初はガーッと感情が出てきても…、この子はたしかに私たちのところへ来てくれたんだ、きっと意味のあることだと、触れあえることで親子に、そして、家族になってゆける。こうしたプロセスがあることを知ったときは、感動したけど、やっぱりそうだったんだという感もありました。日本の医療のなかにこうした価値観がなかったんだから、僕はそれを伝えていく役割があるんだと思いました。この頃から会を開いたり、講演をしたり、本を書いたりと、自分が感じさせてもらったことを形にしていこうという思いが強くなったんです。テクノロジーが進んだことで得たことは多いけど、失ったことも多いんです。人間の根本にある、生きる力によりフォーカスすることで、新しいアプローチで産科と関わっていこうと思うようになりました。
周産期の死に関心をもつようになって、気づいたことは、まず、亡くなっても苦しそうに産まれてくる赤ちゃんがいないということでした。当初、亡くなった赤ちゃんの表情なんて意識したことはありませんでした。やっぱり死は怖いものだったからです。僕らの中にある死って、何か残虐じゃないですか。イスラム国もそうだけど、ニュース性のある死はだいたい残虐です。日常に死が見えない暮らしをしていると、ニュースなどで見聞きした死がイメージをつくってゆくので、その「死」をお母さんからは遠ざけたほうがいいだろうとなるのでしょう。
あと一つは、先ほどお話したけれども、そういうことが起こったときに、早く忘れて次がんばろうというのは…つらいんだということ。これは先送りしている日本と同じで、医療者が目の前の悲劇に蓋をしようとしても、お母さんはそれで解決はできません。できるだけ、その時に事実と向き合えるかどうかなんです・・・、そのために僕たち医療者がどう関わればいいのかが大切、ということでした。亡くなってもやはりわが子です。奇形があったとしても、亡くなってから時間が経って変性していても可愛いわが子なのです。だけれど、そうした子が産まれてくると、「かわいそう」となってしまうのが僕らの意識でした。それでも、僕らがその子をモノでなく、人として大切に扱うことができれば、その子が可愛いわが子になるんです。なっていくのです。医療には正常という枠があります。そこから外れたものが異常です。間違っているわけではないけど、異常を排除しようとする意識がどうしても働いてしまいます。今は一般に普及してきている出産前診断というのは、とりあえず正常らしい人たちは残して、そこから外れた人たちは…。もしかしたら、そこから外れた人たちは天才かもしれないですよ。そこから外れた人たちがすごい才能をもって、この社会の枠組みを壊して、再生させてくれるかもしれないけれども、僕らの社会にはそうした異常を受け入れる余裕がないからか、排除するように思えてしまいます。皆を画一に、普通に、標準化しようとすればするほど、より生きにくい社会を生み出しているような気がします。同時に知っておいてほしいのは出生前診断はビジネスということ。それも、決して社会をよくしようというソーシャルビジネスではない。だって、国では表面的に禁止している優勢思想をビジネスにしているんです。検査費も高いです。それがビジネスとして成り立つということは、私たちのなかに生きづらさがあるからでしょう。検査があっても、自分自身で受ける、受けない。異常があったらどうする、を自分で決められればいいけれど、ほとんどの日本人は、それができません。難しいに決断にせよ、「やった方がいい検査ですか?」「皆さんはどうしてますか?」を周囲を眺めるのが現実です。迷うんだったらやらなければいいと僕は思うけど、それもできず悩んでしまう。テクノロジーが進化して選択が増えても、私たちや社会が成熟しなければ、その進化がはたして幸せをもたらすんだろうか?といつも感じています。自分で自分の生き方を決められない、自分の生き方に責任をもてないというのは、辛いことだと思います。皆さんには、ちゃんと自分の思いをもって、自分で自分の生き方を覚悟をもって選択できる大人になってほしい・・・。周りがどう思っても、自分がこう思うんだとか、こう感じている自分がいるとか…。その時、その時の自分を受容できる大人になって欲しいと思います。
皆さん教育学部だから習っているかもしれないけれども、これはクラウス・ケネルといってね、1970年代の母と子の絆についての研究をした方たち。赤ちゃんが障害をもって産まれてきたときの、母親の変遷を示した表です。最初は「ショック」です。「ショック」というのはすごく大切な感情です。予期せぬことが起こったとき、心と体の動きをとめて、自分を守ってくれる。起こった直後には、後追い自殺のような行為は通常起こりません。その後の「否認」というのは、「私の子は亡くなっていない」とかいうことです。その後に「悲しみと怒り」とありますが、「怒り」は日本ではあまり出ないかもしれないけど、「怒り」は他者に出るときと、自分に出るときがあります。「どうして先生ははやく見つけてくれなかったの!」「自分がもっときちんとしていれば、この子は助かったのに!」という感情です。その後に「適応」、「再起」となっていますが、この通りに感情が出てくるとはかぎりません。ただ、「適応」というのは結果的に「あきらめる」ということです。亡くなったことはどうしようもない、と。それでもこの子がきてくれたのは意味がある。これが「あきらめ」であり、「適応」です。感情の波に打たれないと、やはりここにたどり着くのは難しい。だから、蓋をしないで、波に打たれてみる。もちろん、それを見守る環境も必要でしょう。こういう波って赤ちゃんが亡くなったときだけでなく、自分に予期せぬことが起こったとき、想定外のことが起こったときにも押し寄せてきます。失恋もそうかもしれません。身内の不幸もそうでしょう。志望していた学校や会社に入れなかったこともそう・・・、生きていれば、いろいろあるでしょう。程度により波の大小はあるけれども、想定外のことが起こったときに波がくるんです。でも、日本の場合はとかく波風をたてないようにと蓋をしてしまう。蓋がすべて悪いとは思いませんが、基本的に先送りです。波に打たれちゃえばいいと思うんですけどね・・。引きこもったりとか、怒ったり悲しんだり、その時は乱れていても、これもまた正常なプロセスと知っていると違うと思うんです。「あきらめ」「適応」に行くには時間かかるしね。でも、人には「あきらめ」へと導かれる潜在的な力が備わっているんです。僕たちは感情を出さない、出せない、出させない環境に育っているから、内へ内へと閉じこめてしまうけど、そんなインスタントな対応が、将来のPTSDにつながり、自分をずっと苦しめる原因になってゆく可能性を高めます。もう一度言いますが、子どもが亡くなってしまったけど、真にあきらめるためには何が必要かっていうと、このタイミングで私たちのもとへ来てくれたことはきっと何らかの意味があると、母親と家族が思えることです。意味があると思えると、そこから物語が生まれてきます。それが生きる力です。そのために私たち医療者ができることは、もちろん医療的な解明もそうですが、母親と家族が、安心して波に打たれられる環境を支えるということです。邪魔をしないということです。時間はかかるけど、波に打たれて、あきらめるプロセスを全うできること、それが人間としての成長につながります。適応から再起という成長のプロセスです。これだけ大きなことを乗り越えられたんだから、何があっても私たちは生きてゆける…。乗り越えられるって思うことができます。悔しさとも悲しさもただただ受容してゆく、周りも無理に慰めて蓋をするのではなく、安心して悲しんでもらえるように接する。そこから絆が生まれてきます。だから逆境こそが、成長の源なんです。
2002年に「誕生死」という流産・死産をした12家族が実名で自分の体験を綴った本が出ました。「誕生死」という言葉は、医学用語ではなく、この本のために男性コピーライター考えた流産・死産を表す言葉です。この言葉が体験者に伝わったんです。亡くなっても生まれてきてくれた…みたいな少し優しい語感があるでしょう。「私は死産しました」「流産しました」って使いにくいフレーズなんです。「誕生死しました」というと、少し使いやすいのでしょう。言葉は大きいです。医学用語にはこうした配慮がありませんでした。でも、最近になって変わってきています。たとえ統合失調症は、以前は精神分裂病といわれてたんです。流産・死産も冷たいですよね・・・。「流れる」には、子どもの死が、お母さんの抱えている業も一緒に流してくれる…という意味が昔はあったそうですけど、やっぱり冷たいです。 この「誕生死」が出版されたことで、30年も40年も50年も前に流産・死産した人たちの蓋があいたんです。日本には、自分の悲しい体験を周囲に話したり、周囲が積極的に聞こうとする習慣はありません。周りに語って、一緒に聞いて、一緒に泣いて…という展開はなかったのです。周囲から、「大丈夫ですか?」と言われたら「大丈夫です」と言ってしまう文化ですよ。「大丈夫ですか」なんて聞かれたら、「ダメに決まってるじゃないですか!」と言えればだいぶ楽になれるだろうけど、一度「大丈夫です」って答えたら、大丈夫じゃなくても、それからは大丈夫を演じなければいけないからです。そうやって流産・死産の体験者は自分の体験に蓋をしてきたのです。でも、30年前、40年前のことでも、時間がたったから忘れているのかと思ったら、その人たちはその時のことを鮮明に覚えていたんです。奥深いところに閉じこめていて、蓋を開けたらバーッと出てきた。僕が開いた会でも、何十年前のことを、昨日のことのようにお話してくれる方がたくさんいらっしゃいました。その時には向き合えなかったわが子の死と、ようやく安心して向き合える時がきたんです。そこから新たなグリーフワーク、グリーフというのは大きな悲しみで、グリーフワークとはそのプロセスを歩んでゆくこと。つまり、波に打たれることです。そうしてようやく適応・再起へと歩み始める。これが蓋をすることは先送りしているだけで、解決するということではないという意味です。ただ、考えてみれば、30年前には安心して波に打たれる環境はなかったでしょうから、その時は蓋をしてよかったのかもしれません。思わずして蓋が開く機会をえて、新たな悲しみと安心して向き合えることができたのが、よかったことなのかもしれません。 ただ、数え切れない方が蓋を閉ざしたままでいるし、蓋を閉ざしたまま亡くなっているのです。
次にエビデンスについてです。エビデンスとは根拠のことです。たしかに、医療では効果のある治療をするのは大切なことですけれど…。あたりまえのことですが、それで全員が治るのではないということです。8割が治る治療ってすごいけど、2割は治らないということです。治らないだけじゃなくて、その治療をしたから逆に悪くなる人もいます。そして、毎年2千人くらいの人は医療過誤で亡くなっています。エビデンスがある治療といってもそれが医療です。医療とは万人に効くものではないし、人がやることだから過誤もおこります。頭ではわかっていても、それが自分や自分の身内に起こると受け入れられない。それも自然なことでしょう。最善の医療を提供することは、結果を保証することではありません。医療だけでは解決しない。だからケアが必要なのです。そのケアにはエビデンスはありません。こう関わればうまくいくというマニュアルはありません。僕らに大切なのは、たとえば赤ちゃんが350グラムの正常な妊娠20週であっても、お母さんはそれぞれここまで生きてきた時間が違うという意識をもてることだと思っています。パートナーとどのように知りあって、どういう状況で妊娠をして、ここまで生きてきたのか、この妊娠やお腹の中の子のことをどう思っているのか・・・。そんなこと医療と関係ないじゃないとかと思うかもしれないけれど、一人ひとりをその人の物語の中で捉えないと、表面的な正常、異常でしか見れない、ただの医師になってしまうかもしれない。それでいいじゃないかという考えが多いのかもしれませんが、僕はそれじゃつまらない(笑)。物語りで捉えようとすることで、一人ひとりとの間に関係が生まれてくるからです。母子ともに元気が一番大切だけれど、それだけだと、生きる力、生き抜いてゆく力にまで繋がりにくいんと感じています。医師がそこまでする必要はないかもしれません。そこは僕のこだわりなのかもしれません。今でも病院では「指導」が中心ですが、指導やお説教で、人を変えることは難しい、というかできないんじゃないだろうか。本人の気づきがなければ、かわらない。妊娠中って、そういう気づける可能性に満ちている期間だと思っています。妊娠、出産までは、医療者の指導でなんとかいけるかもしれませんが、子どもをつれて家に戻れば、自分でやっていかなくてはいけないのです。だから、意味や物語の視点がかかせないと僕は思います。医療だけでなく、教育もたぶんそうですよね。学習を通して、知識を応用してゆく力、それこそ生きる力になるでしょうが、そこへ発展してゆくには、教師がケアや物語の意識を持っているかが大きいはずです。
こうしたケアや物語という意識をもって、周産期の死に関わることにエビデンスはありませんが、生きて産まれてきた赤ちゃんでも、死んで産まれてきた赤ちゃんでも、望まれた赤ちゃんも、望まれない赤ちゃんでも同じように大切に扱おうというコンセプトは僕が最終的に行き着いたところです。今までであれば、亡くなった赤ちゃんは水場に置かれていた。望まぬ赤ちゃんで中絶だったら、モノのようにそのまま見捨てられていた。望まれて、元気で、幸せに産まれてきた赤ちゃんにだけ「おめでとう」と言っていたのです。それって大人や社会の都合じゃないかと。子どもは、そんな都合とは関係なく、天文学的な確率と、何らかの意味をもって、一時ではあってもこの世に生を授かったのだから、やっぱり「おめでとう」です。だから、途中で亡くなっても、中絶であってもモノじゃない。そう思えるようになってから、自分の気持ちが晴れていったんです。どんな状況で産まれてきた赤ちゃんにでも、「おめでとう」って、丁寧に大切にケアすることで、産んだお母さんだけでなく、僕たち医療者も癒されてゆきます。不思議です。言葉はなくても、自分が産んだ赤ちゃんが大切にされると、自分が大切にされた感じがする。そこに僕のひとつの結論がありました。
この写真は18週くらいですね、亡くなった赤ちゃんです。お兄ちゃんも一緒に亡くなった赤ちゃんを囲んでいる。こんなふうに子どもに亡くなった赤ちゃんを見せるということは考えられませんでした。タブーでした。大人だって死がこわいのに、子どもがこわくないはずがない、トラウマになる。もっとものようだけど何の根拠もないし、そこには実践もない。やっぱりそれも大人の都合です。でも、逆なんです。大人には…たくさんの余計な情報が入ってきているから、死は残酷でこわいものになっている。でも、子どもはピュアです。僕たち医療者が亡くなった弟を大切に扱うことができれば、お兄ちゃんにとって、亡くなった弟は決してお化けじゃなくて、やっぱり大切な弟なんです。 お父さん、お母さん、お兄ちゃんが、こうして18週で亡くなった子を囲んでいますが、このなかで一番最初に受け入れられたのがお兄ちゃん、子どもでした。僕はこうしたケースに多く関わってきましたが、子どもって死への偏見が少ないんだと感じます。亡くなっても自分の大切な弟なんだ…という感じが伝わってきます。次はお母さん、一番受け入れられないのはお父さん、大人の男性なのですよね。大人の男性って立場を求められるから、そこでは、父親だから、男だから、大人だからしっかりしなければいけないとかね。僕が支えなければいけない、と。その状況のなかで素の自分でいられないから、難しいんだと感じます。最終的に崩れるのも男性なのだけれども、男性はその場では感情を出すことがなかなかできません。お兄ちゃんは相当語るんです。自分の弟が焼かれてしまったあとも、お墓に入った後も語りかけてるって、後でお母さんが教えてくれました。お兄ちゃんが、亡くなった弟の仏壇に語りかけるのを聞くと、お母さんも嬉しくて涙がでてくるそうです。「先生、皆で会うことができてよかったです」。でも、やっぱりお父さんはなかなか語ろうとはしないそうです。
このへんで一回質問タイムにします。あっ、今皆さんに見せた写真はどれも、お母さんが「使ってください」って言ってくれたものばかりです。私たちの大切な子どもが確かにいたことを皆に知ってもらいたいという気持ちがあるからです。 では、前半はこの辺で。
【司会】竹内さん、ありがとうございました。それでは質疑応答の時間にさせていただきます。前半の竹内さんの講演を聴いて、質問や何か疑問がある方はその場で挙手をしてください。
【学生】教育学科の3年のシバヤマと言います。自分は先生と同じようにといいますかまだ教員を目指している立場なんですけれども、学校の現場でもっと死について考える機会をもっと与えるというか、先生みたいに考えるきっかけを与えたほうがいいんじゃないかなと考えて、今、論文を書いたりしているのですけれども、やはり周りから「何でわざわざそんなことやるのか」とか、あるのですけど、先生がこういう講演会をやっているのと同じように、批判とかはあったと思うのですけど、何が先生を動かしている原動力というのが何になっているかを教えてください。
【竹内】助けることができなかった赤ちゃんたちが、ピンチになると守ってくれていると感じています。何かが起こると、「医療ミスなのじゃないかな」と思う風潮があるでしょうし、医者はたくさんのなかのひとりだから何とも思わないんじゃないかと思うかもしれませんが、自分がみていた赤ちゃんが亡くなるのは、医療者にとっても辛いし、悲しいことです。僕が帝王切開をされたお母さんが手術後に肺血栓症で亡くなったこともあります。全力をつくしたけど、どうすることもできなかった・・。妊娠中からかかわってきた方なので本当に辛かった・・・。お母さんが亡くならなければ、たくさんの家族の時間があったわけでそれも全部奪ってしまったんです。僕もすごく苦しかったけど、ご主人、家族とも向き合わなければならなかった・・・。それも大切な仕事ですし、仕事を超えて人としてできうる関わりです。原動力は、僕のもとで亡くなったお子さん、そしてお母さんの存在ですね。
批判は言われましたね。いろんなことをね。今はもう始めて十年以上たっているし、周産期のグリーフケアも浸透してきているので、そういうこともなくなりましたが、最初の頃ですよね…2000年くらいかな、今から何年前でしょう。15年ぐらい前。15年前だから、僕はまだ40歳前後です。その頃は、周産期の死に関わっている医療者はまずいなくて、キリスト教系の病院の牧師さんくらいじゃなかったでしょうか。僕はまだ40ですよ。この人が死について語る?みたいな感じで、講演で僕が紹介されたら「エッ?」って。「あなたですか?」みたいな雰囲気でした。自分にも自信がなかったんでしょうね。ただ、死は偉大な方が、荘厳に話さなくてはいけないみたいな感じがいやで、誰もがもっと普通に語っていいテーマじゃないかと。人が生きていくためには必要なことだから・・・。そういう意味から、批判があっても、死はこうあるべきじゃなくて、自分が感じたままの死を話せたのはよかったと思っています。
【司会】ほかに質問のある方はいらっしゃいますか?
【学生】教育学科1年のイノと言います。先生が、患者さんで自分の子どもが亡くなっちゃったという話をするときに、とても患者さんの気持ちとかがワーッとなってしまうと思うのですけれども、そういう方と接するときに先生が気をつけていることは?
【竹内】余計なことを話さないということですね。例えば、僕はグリーフケアのカウンセリングの場をもってるんですが、最初のカウンセリングのときは場合によっては、お母さんが最初に部屋に入ってきて、50分間、何も話さない方がいました。その間、僕も話したり、尋ねることはありませんでした。普通の妊婦さんの外来では、時間も基本的にはこちらから、いろいろと話したり聞いたりします。でも、カウンセリングでは、聴くが中心で、できればあちらから第一声を発してもらう。いつもは話してるのに、急に聴くに変えるって、実はとても難しいことなんです。ただ、「そうか・・・」って聞いている。あと、たとえば「あぁ、それはつらかったけど、もっと大変な人がいるからね」とか、まぁそんなことは言わないけれど、評価したり、まとめないことが大切です。日本人ってね不幸に対してはもっと大きい不幸で中和しようとしたり、幸せに対してはもっと大きな幸せで薄めたりしてしまう…。そんなところがあるんですよ。相対的幸福みたいな。それはダメですね。難しいけど、基本的にはただただ聞いているって感じです。安心して聞いてもらえる場があるって必要だと思うんです。皆さんもそうだと思うけど、何かあったときに、それを話せる人と話せない人がいるじゃないですか。途中で「っていうか…」って遮られたり、「こういうことだよね」とかまとめられちゃったりする人には、安心して話せないでしょう。お子さんを亡くされたお母さんは、自分の両親や旦那さんともなかなか本心を話すことができないんです。だから、安心して話せる、安心して過ごせる時間になるように思っています。50分何も話さなかった方だって、自分のなかでいろいろな思いがリフレインしていたのかもしれません。 何も話さない=何も対話しないではないんです。何も話さなかったけど、カウンセリングに入る前と、後ではきっと何かが違っている。そんなこと気をつけています。
【司会】ほかに質問のある方はいらっしゃいませんか?
【学生】教育学科1年Aクラス・イセヤです。竹内さんが海外に視点を置いているようになったきっかけというのは何でしょうか?
【竹内】ただ、昔から、小さい時から行きたかったんですよね。今は海外の情報が溢れているし、手軽に海外に行けるようになりましたが、僕のころはそうではなかったんで、「世界の旅」シリーズの写真なんか見て、「すごいなぁ」って憧れてたんですよね。ただ、自分が海外に出るというリアリティは子どもの頃はなかったのです。高校の時にホームステイでアメリカに行く機会があって、その巨大さに圧倒され、大学に入って最初に放浪したのがヨーロッパでした。予定もないバックパッカーの旅でしたが、旅を重ねていくうちに、だんだん途上国に目がいくようになりました。そして実際に貧困の中に入っていくと、自分のなかで形づくられたイメージと違っていたんです。きっと「かわいそう」と、思っていたんでしょうが、人は生き生きとしていたからです。あと、日本って何でこんなにつまらない国なのだろうと思っていたけど、海外から見ると、日本って素晴らしい国なんだって誇りをもつことができました。それは自分にも言えますね。帰ってくると「何だよ…みんななんか神妙な顔をして」みたいな、ね。海外では、日本で当たり前のことが当たり前じゃないから。天候などの理由で2,3分電車が遅れただけで「申し訳ございません」なんて、そこで謝るのが日本なんだろうけど、そんな国、他にないわけです。僕たちきちんとしすぎじゃないのってさえ思っちゃう。振り返ってみると、きっかけは、異質なものに憧れたことだと思います。今もそうなんですけど、自分と違うものに関心があるように思います。今、一番関心があるのは、生き方です。人の生き方もそうだけど、自分自身、「竹内正人」の生き方にすごく関心がありますね(笑)。
【司会】ほかに質問のある方はいらっしゃいますか?
【学生】教育学科3年の大塚と申します。今、死についてお話いただいていると思うのですけれども、これからたぶんここにいる全員が必ず、子どもたちの死ではなくても、死に向き合う機会というのが必ずあると思うのですが、自分も先日、身内が亡くなりまして、受け入れるというか、乗り切るという事が自分はまだ全然出来ていません。先生はそういうことを見てこられたと思うのですが、そういうものというのはどのように受け入れていったらいいのか。先生なりの考え方を教えていただければと思います。
【竹内】僕が死にかかわって感じたことのひとつは、死が終わりじゃないということなんです。波に打たれてゆけば、時間はかかっても、そこからまた新たな意味が生まれ、物語が始まるんです。その方との関係が深ければそれだけ波も大きくなるでしょう。それは必要なプロセスなんだということを知っておいてほしいです。急がないことです。生きていれば、誰にでもいろんなことが起こります。到底受け入れられそうもないことも起こるでしょう。そんな時もできるだけ自分に介入せず、波に打たれて、そのままの自分でいれるのが一番いいと思います。「こんなふうに考えちゃう自分ってどう?」でなく、「自分はこう感じているんだ」「こう考えているんだ」と、そのまま受け入れられるといいですね。奥深いところから湧き上がる感情を、循環させることは大切だと思うんです。その時点では何が正解かはわからない。それでも奥深くにある感情や考えは、その時の自分自身です。世間的にはいただけない非人間的で、冷たい考え方であっても、そのときの自分がそう思っているのであれば、受け入れるのがいいと思います。いずれ、そうした思いが昇華して、亡くなった方との新たな物語が育まれていくには、その時のそのままの感情を受け入れて循環させてゆかなければならない。そんな感じで、自分の中では、辛い時ほど出しっぱなしにする、を心がけています。
【司会】藤本先生、お願いします。
【藤本】さっきの海外への関心の質問のなかに、お医者さんになられるときに産科を選ばれたのは消去法だったと言っていらっしゃいましたよね。何はやめて、何はやめて…というのをかいつまんでもいいのですが、ダメだったものを教えてください。
【竹内】最初は外科を考えたんですね。ただ、かっこいいかなと思ったからです。でもその頃は外科の希望者が多かったんです。で、ここでの自分の役割はあまりないなって、今度は整形外科の医局へ行きました。それで教授にお願いしますと言ったのですが、何かその教授と相性が合わないなって感じて、これは違うなと。変な話ですが、直感です。そして、昔からの夢もあり、小児科へ行きました。ただ、当時の小児科は白血病などの血液疾患が専門だったので、ちょっと僕の世界とはとちがうな、と。そんな些細なことです。あとは眼科にもちょっと行ったのですけれども、研修で患者さんの目を見ているうちにクラクラしてきたので、ここは向いていないな…と、そんな感じでした(笑)。最後が産婦人科でした。女性だけというのが抵抗あったし、「えっ~産婦人科?」みたいな(笑)、何かイメージもよくなかったので、絶対に選択しないと思ってたんですね。それで、学生実習のとき、今後産婦人科に関わることはないだろうからって、一生懸命だったんです。やっぱり肌にあっていたのでしょうね。この仕事は合うかもって感じていたんです。あと、人気がなく他に誰も希望する学生がいなかったことも決め手になり、あぁ、ここなのかなって、という感じで入った次第です。あと、産婦人科でも子どもと関係あるな、ということもありました。はい。産婦人科でもらえる初任給が4万円くらいで、50万円もらえる科もあったんですが、それは魅力ではあったけど、やっぱり自分に適正な場がいいと思いました。いい選択でした(笑)