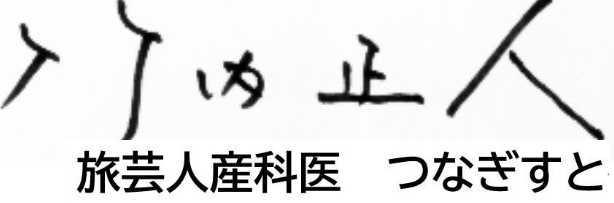NOTE ノート
「誕生死について考える」
〜家族に寄り添うサポートとケア〜 第3回「看護と社会」研究全国集会 基調講演 2006/11/26
これまで医療という視点で「妊娠」「出産」を見てきたなかで、
無意識のうちに切り捨ててきたものがあります。例えば、死産や流産、子どもが五体満足ではなかった。
そのような予期せぬ結果や望まれない結果に、医療ではどう対応していいのかがわかりませんでした。
それは、医療が常に結果を求めるものだったからかもしれません。
もう3年ほど前になりますが、私は産科を離れて、1年間、介護、ターミナルケアという、生とは対極にあると思われる死に近い現場です。
そこで改めて感じたことは、人が産まれて、生きて、亡くなっていく、という根っこには、
共通した本質、共通した流れがあるな、ということでした。
ここ数年、医療の現場で働くスタッフに勤労意欲、モチベーションの低下という状況が広がってきています。
特に命を扱う産科ではそれが顕著で、産科医、助産師、看護師が、現場を離れ立ち去るということが、目立つようになってきました。ある意味、起こるべくして起こってきた現象だと、私は思っています。
医療現場で亡くなった命は「人」はなく「モノ」になってしまう
産科医になった当初、これから発展しいく医学・医療を駆使すれば、僕はすべてのお母さん、そして、子どもを救うことができるようになる、と本気で思っていました。
ところが、時を過ごすうちに、人が人であるかぎり、すべての命が幸福な結末をむかえるわけではない。そんな当たり前の事実と、医学の限界を繰り返し突きつけられることになりました。
産科というのは、新しい命を迎える幸せな場と思っていたのに、「生」のとなりには厳然として「死」の存在があるのです。
長い間、流産は日常的に遭遇することでありながら、仕方ないこととして「死」を意識することもなく、死産、新生児死亡の場合は、あえて、「死」を意識しないようにして、関わってきました。
それでも、「死」ときちんと向き合わなければ、僕は産科医として働くことができなくなる・・・
と感じるようになっていったのです。
妊娠22週でお腹の中で子どもを亡くされ、死産を体験されたお母さんからうかがった話しです。
「出産の時に、外来で働いている助産師さんや看護師さんまでが見学に来ていました。
私のようなケースが珍しいのか、興味本位で集まっているようでした。
私の足下で出産までの時間、ぺちゃくちゃと関係のないおしゃべりをしていました。そして、出産しトレーにのせられた私の赤ちゃんを、まるで死んだ猫か犬でも見るような目でみていました。」
「私は彼女たちの表情を見ただけで、赤ちゃんに会ってはいけないような気がしてしまいました。」
彼女の場合、お子さんがお腹の中で亡くなって1週間くらいは「死」を気づかず、妊婦健診で突然に赤ちゃんの死を告げられたそうです。そんなことを告げられるために病院に行ったのではなかったのに。
産まれてきたとき赤ちゃんはすでに変性していたそうです。死産に、立ち会ったスタッフはその赤ちゃんを見たときに顔をしかめてしまいました。
でも、一番怖いのは誰でしょう?・・・そうです、お母さんですよね。
お腹の中でのわが子の死を1週間も気づくことができなかったのですから。そういう状況を感じ取れない医療者が死産を関わる。だから、形だけみて顔をしかめてしまうのでしょう。
わが子を温かく受け入れてもらえないのは、どのような状況であっても、とても、悲しいことです。
彼女は続けました。「何よりも赤ちゃんを大切に扱ってほしかったと思います。私が赤ちゃんを出産したとき、『出た』といわれました。私は出産したという気持ちだったのに・・・、人として扱われなかったようで、すごく悲しかった」。
医学の中でお産を扱っていると、それまでに元気であっても、赤ちゃんが亡くなった瞬間に、「産まれる」かる「出る」にかわってしまうのです。
医療者の意識の中で赤ちゃんが「人」から「モノ」になってしまうからでしょうか。
赤ちゃんは死んでしまうと、人として扱われなくなっていたのです。ところが、お母さんと家族にとっては亡くなってもわが子であることにかわりはありません。
この温度差がとても大きいんです。大きすぎるんです・・・・。
ただ、医療者がはじめからそうした意識だったわけではないでしょう。私たち医療者もそれぞれ、普通のひとりの人間なのですから。ただ、医療の中にいて、きちんと意識をしていないと、知らないうちに生き死にへの、デリカシーがなくなってゆくのかもしれません。
悲しみの感情を封印しても一生引きずってしまう
流産や死産を経験した場合、病院の中ではなかなか悲しみの感情を出すことができません。
思いっきりワーッと泣いたりすることは難しいのです。寄り添ってくれる看護職は多いと思いますが、病院には、逆に「まだ若いから」とか、「次があるから」「早く忘れましょう」などといった言葉で感情を出させないようにする環境がまだ残っているかもしれません。
なぜそうするかというと、特に理由はなく、そうした対応がいいんだろうと漠然と思っているからなのでそうが、目の前でずっと泣かれていても困るし、どう対応していいのか分からないので、まとめようとしてしまうのかもしれません。
ケネルとクラウスの「母と子の絆」で紹介されていますが、重症児が生まれてきたときの両親の反応は、まず「ショック」があって、その後に「否認」がきます。否認とは、私の赤ちゃんは障害(死んで)なんてない、それは私の子どもではないんだという感情です。
その次に、「悲しみ」、「怒り」がきて、「諦め」「適応」、そして「再起」がくるとなっている。
どの人も同じプロセスをたどるわけではなく、感情の推移には「共通性」と「個別性」があります。
当たり前だけど、それぞれで違うんです。様々な感情が行ったり来たり、戻ったりと繰り返すのもとても自然なことです。
あと、とても大切なことは、感情が変化してゆく時間には目盛りや目安がないということ。
例えばショックは1週間ですよ、その後の1週間が否認の時間ですよ、その後の1ヶ月は悲しみと怒りで、3ヶ月したら悲しみが半分くらいになって、適応できるようになって、半年たてば落ち着きいてゆきますよ、という目盛り、目安がないんです。
このプロセスは、予期せぬ苦しみとか悲しみに直面したときに、人が受ける正常な心の変化なのです。ところが、驚いたことに、このような悲嘆のプロセスを、現場の医療者の多くが知らない。あるいは、知っていてもそれを意識して仕事をしていない。
日本人には、「自分さえ我慢すればうまくいくのであれば・・」というメンタリティーがありますよね。私たち日本人は、自分の中の悲しみ、怒りといった感情を、できるだけ出さないようにして過ごしている人が多いと思います。
だから、感情を前面に出す方を目の前にしたとき、私たちは、どう接していいのかがよくわからない。医療者も同じかもしれません。
「なんでわからなかったんですか」「医療ミスじゃないですか」「どう責任をとってくれるんですか」といった類の、「怒り」を見せられたとき、それを、正常な悲嘆のプロセスと理解して、受容的に対応できる個や施設はあまりないかもしれません。
悲しみの渦中にいるものに、大丈夫のはずなんかないのに、「大丈夫ですか?」って普通に聞けてしまうのが私たちなんです。何て言っていいかわからないときには、何も言わなくていいんですけどね・・。
あなたは、大丈夫ですかと聞かれて、「大丈夫のはずないじゃないですか!」って、答えられますか?
もし、「ありがとうございます、大丈夫です・・・・」と答えてしまったら、その人に対して、これからは大丈夫じゃなければいけなくなります。もう、その人には心を開けなくなりますよね。
「大丈夫ですか?」って聞いた人も、どうしていいかわかないから、そう聞いただけかもしれません。多くの場合、「そんなはずないじゃない!」って返させるとは思ってないでしょね・・・。仮に、もし、そう返されたとき、適切に対応できる人は少ないと思います。結局、この社会では、「大丈夫」を装って生きていくことが、求められているのでしょう。
ところが、こうした悲嘆のプロセスを十分踏まなければ、諦めでもある、真の適応と再起はおこってこない。悲しみつくす、怒りまくる。ひきこもる。見苦しいかもしれないけれど、そうした時間にも意味があって、そうした感情の表出が、次の段階へと運んでいきやすくしてくれるのです。
ポストトラウマティックストレスシンドローム、PTSD、心的外傷後ストレス障害という言葉がありますが、その対応として、まずはその事実になんとか向き合い、様々な感情を湧きあがらせることから始めます。
30年、40年も過去に蓋をしていた事実や体験がワーっと出てくることで、もう忘れてしまったかと思っていた、「悲しみ」、「怒り」が湧き上がってくるんです。そこからようやく悲嘆のプロセスが始まります。感情の変化に目盛りなんてありません。
介護老人施設で働いていたとき、私は入所している、おばあちゃんたちにお産の体験を聞いていました。すると、90歳をこえたおばあさんが、20歳で体験した死産の経験を話されたりする。そのことに触れないよう生きてきただけなんです。話し出すと、いろいろな思いが蘇ってくるんです。
「先生、こんな年になって、そんなこと思い出させて可哀想じゃないですか」と、最初は周囲のスタッフからそう言われました。でも、自分の奥底に閉じ込められてきた感情が丁寧に受けとめられてゆくことで、おばあちゃんの心が、表情が徐々に柔らかになっていったんです。
人は誰もが無意識のうちにたくさんのことに蓋をしながら生きてきています。辛く悲しい体験を乗り越えること、次のステップへ行くということは、忘れようとすることではなく、そうした体験と共存していくことなんだ、言われるようになってきました。
でもやっぱり感情を表出できる場がなかなかない「自分さえ我慢すれば・・」の日本では、感情に蓋をしながら生きていくことのほうが、普通なのでしょう。
死産・流産であっても、その子の母親という意識を持ち続ける
医療の中で予期せぬ死産、流産を含めて起こった場合、よく「仕方がなかった」という言葉が使われます。
双子の赤ちゃんのケースですが、妊娠18週のときにふたりのうちのひとりが、産まれてきても生きていくことができない奇形があることがわかりました。それ以降、お母さんは、生きていける子の方だけに意識をもっていき、双子とは思わないようにして妊娠期間を過ごしてきたそうです。
妊娠29週に、別の理由で帝王切開にたったとき、奇形のあった子は、そのまま息をひきとりました。「情が移るといけないから」「見るとかわりそうだから」と、お母さんはその子を見ることさえ、もちろん、抱きしめることさえしませんでした。周囲もその子のことについて、一切ふれなかった。
お母さんは、しばらくは、未熟で生まれてきた子にだけに気持ちを注いできました。
2年、3年がたち、その子が元気に育ってゆけることがわかり、気持ちに余裕がでてきた頃になって、もう忘れていたはずの、奇形があった子への感情が湧き上がってきたそうです。
帝王切開の後、医師からは、「奇形があったんで仕方ない」と簡単に説明され、ある医療スタッフには「1人だけでも助かったんだからよかったじゃない」と言われたので、そうなのかな、と思うようにしてきたけど、結局はどうにも受け入れることができなかったんだと・・・・
夫には「今さら何を・・」と言われそうで、何も伝えられなかったそうです。
病気で産まれてきた子に対して、私たち医療者は「仕方なかったケースです」と話すことがあります。医学的にはそれで完結してしまうからです。でも、お母さんの中では、そうではない。少しも完結なんかしないんです。
「仕方がない」という言葉は、切り捨てられたように感じで、受け入れがたいようです。
「仕方がない」は、その子を授かった意味がないように聞こえて、受け入れがたいようです。結果はどうしようもないにしろ、それでも来てくれた「意味」を紡ぐことは大切なことです。
もし、医療者とお母さんの間に信頼関係ができていれば、もし、かかわる医療者に、生きてゆけなくても、家族にとっては大切で意味のある命なんだという意識があれば、「仕方がなかった」は、実はなかなか使えない言葉です。
手はつくしたけどという観点から、「どうしようもなかった」という言葉を使うかもしれません。「どうしようもなかった」と「仕方がなかった」は、似ていますが、まったく違う語感をもった言葉です。皆さんにも、その違いを感じてほしいと思います。
妊娠35週で胎盤が急に剥がれてしまった方が、「痛い、痛い」って言いながら、ご自宅の近くの病院から私が以前にいた周産期センターに運ばれてきました。
超音波を当てると心拍はすでになく、赤ちゃんは亡くなっていました。
家族には事実を話したのですが、私はその場でお母さんに言うことができませんでした。出血があり、このままだとDIC(出血がとまらなくなる状態)になってしまうので手術室に直行しました。僕は「胎盤が剥がれてきているので、すぐに帝王切開をさせてください」とお母さんに説明しました。
お母さんは動転して、「先生、赤ちゃんは大丈夫ですよね!」と語気をあらげました。僕は一拍おいて、「・・・赤ちゃんの心拍は動いてないかもしれません」と言うのが精一杯でした。
医療者として事実を正確に伝えるのは、大切なことです。それでも、それができない時がある。どのようなタイミングで、どんな言葉を使って伝えるのかは大切なことです。
緊急手術となり、すぐに赤ちゃんをすぐに娩出しましたが、やはり、赤ちゃんは亡くなっていました。ただ、どんな状況でも、赤ちゃんって、苦しそうな表情で産まれてこないんですね。この子も、胎盤が剥がれて急に酸素がこなくなった、いわゆる窒息のような状況だったのですが、実に穏やかな表情で、血の海となった子宮から産まれてきてくれました。
こういう場面に多く立ち会っていますが、実は、苦しそうな顔で生まれてきた赤ちゃんを見たことがありません。どの子も、穏やかで、神々しい感じさえする。命を全うしたって表情をしているんです。
そんな経験を重ねてゆくうち、亡くなったからといって、お母さん、家族が子どもと会うことができない、抱っこもしてもらえないということを、とても、不自然に感じるようになっていました。
お母さんは手術後に輸血を受けながら「この子は動いていたんです・・」って叫んでいました。そういう状況の中で、私は亡くなったお子さんをそっとお母さんの枕元に連れてゆきました。事実を目の前にして、彼女は嘆き悲しみましたが、赤ちゃんに触れ、しっかりと抱えました。
ところが、小一時間ほどたつと、子どもをしっかりと抱っこしている彼女の表情は和らいでゆきまました。2、3時間もすると、僕も「可愛いね」という言葉が違和感もなく出せるようになっていました。それを聞いた彼女にも少しだけ笑顔が見られるようになりました。触れるって、すごいことなんです。
覚えておいてくださいね。
亡くなっても「モノ」じゃないんです。やっぱり、「人」なんです。
誕生死・・・亡くなっても産まれてきてくれた赤ちゃんの視点
今までの医療現場では、日本社会では、子どもが亡くなると「モノ」となっていました。
情が移る、情が残るといけないから、何も残さなかったし、会うことも、抱くこともできなかった。
でも、本当にそれで良いのだろうかと思い、僕のいた病院では、亡くなった子でも、生きて産まれてきた子と同じような意識で接してみようと決めました。赤ちゃんと一緒に写真も撮ったり、沐浴をしたり、足形や手形を取ったりしました。すでに死後硬直で手が開かず、手形はうまく取れないのですが、きれいに取ることが目的ではありません。
何年後かに、この手形を見ることができたときに、「あの時先生と一緒に手を広げたんだ」とか、「赤ちゃんの手、温かかったな」とか・・・、手形や足形を見ることで、その時に戻ることができる、この子は、確かにわたしのところに来てくれたんだって思える。
そんなことが大切じゃないかなと感じました。
胎盤早期剥離の方はそれから、2人のお子さんが授かったのですが、自分は3人のお母さんという意識をしっかりもっていらっしゃって、それを子どもたちにも伝えている。
「誕生死」という言葉が今注目され、体験者の方たちに広く受け入れられています。「誕生死」は2002年に三省堂から出版された本のタイトルがで、医学用語ではありません。
今までの「流産」「死産」という言葉は、亡くなった赤ちゃんを死の側から見た医学の言葉でした。
だから死産したとか流産したという言葉はお母さんには使いにくい。ところが、誕生死というのは、亡くなっても生まれてきてくれたと、子どもを生の側から見つめた、英語の「スティルバース=stillbirth」に近い語感を持っている言葉です。
スティルというのは「それでも」という意味があります。そしてバースは「生まれる」
それでも生まれてきてくれたといいうことになります。亡くなっても子どもは「人」という意味なんです。
だから、お母さんには、受け入れられやういのでしょう。そうしたちょっとした言葉の違いで、同じ事象でも、意味も、感じ方も違っきます。医学用語で話していると、そうした言葉のもつ感覚やそれに伴う感情を、意識できなくなってしまうことがあるのです。
いのちが来てくれたことに意味がある
どういうお産がいいとか、どういう死に方がいいのかというのは難しいですね。命に関していえば、 70年、80年生きることができたからいい人生というわけでもない。その命がよかったかどうかは、その人が、そして、その人の近しい人がどう感じるかですよね。そして、どういう死に方がいいのかは、その人がどういう生き方をしたのかということなのでしょう。
亡くなった赤ちゃんはどんな子でも、すごく幸せそうな表情で産まれてきてくれる。これは、産科医をしている私にとって大きな驚きでした。短い時間でも精一杯、生き抜いたから、こんなにいい表情で死んでゆけるんではないか・・・
そう感じるようになってから、「死」に対する意識、お母さんと、子どもへの姿勢がかわってきました。生きて産まれてくることはできなかったけれども、その子が来てくれたことにはきっと意味があるのだろう。そう感じとれることで、来てくれた命に素直に祝福できる気持ちを持てるようになりました。そうなってから、お母さん、家族とのかかわりもしっくりくるようになり、僕自身が楽になってゆきました。
平成15年に妊娠21週でふたごを亡くされた方がいました。
上にお兄ちゃんとお姉ちゃんがいて、新しいふたりの家族が来てくれたのを楽しみにしていたのに、妊娠21週で破水をし、その日に生まれてきて皆で見送りました。
その方が、翌年の平成16年にまた妊娠して私のところに来てくれました。
「ああ、また来てくれたんだね」って家族で一緒に喜んだのですが、今度の赤ちゃんは妊娠21週の健診で、心拍がなくなっていることがわかりました。
お母さんもお父さんも、それこそボロボロでした。産まれてきてくれた赤ちゃんは、亡くなって1週間ぐらい経っているようで変性もしていて、おへそが首と足にグルグル巻きになっていて、苦しそうな体勢なんですが、でも、表情はやっぱり苦しそうではないんです。とってもかわいい赤ちゃんでした。
産まれてきた赤ちゃんを温かいタオルで優しくつつんで、「生まれてきてくれたよ。可愛い子よ」と、グルグル巻きになっている、おへそをゆっくりとひもときながら、お母さんの胸のうえに返しました。
お兄ちゃんとお姉ちゃんは、お母さんの手をしっかりと握りしめ赤ちゃんを見つめています。温かい目で周囲が見守れば、亡くなっても、かわいい赤ちゃんになってゆくんです。
1ヶ月くらい経ってから中2のお兄ちゃんと、小4のお姉ちゃんから手紙をもらいました。
お兄ちゃんは「先生、お元気ですか。僕は元気です。○○が産まれたとき、先生が温かいタオルで抱っこしてくれて嬉しかったです。○○は苦しそうだったけど、かわいかったです。ユウキが帰ってきた夜は、1時くらいまで起きていて、お線香とろうそくが消えないように見ていました。ユウキは死んでしまったけど、僕の大切な大事な弟です」
と、そして、お姉ちゃんからは
「竹内先生、元気で頑張ってお仕事をしていますか。○○が産まれたときにあたたかいタオルを用意してくれてありがとう。最後におうちに帰るときに手を振ってくれてありがとう」
温かいタオルで包んであげて、家族に返してあげる。そうして見守っていると、途中で、タオルが温かくなくなってくると、温かいタオルに替えてあげたくなってくる。
そういうところが子どもたちには、伝わっていったようです。
「最後に手を振ってくれてありがとう」とかね。そうやって私たちの弟を大切に扱ってくれたということですよね。私のところにきて、3人の妹や弟たちが亡くなっているのに
「竹内先生、元気で頑張ってお仕事をしていますか・・」ですよ、僕も目頭があつくなってきました。
自分の価値を押しつけない
「流産」という言葉は、今は冷たくて辛い語感しかないかもしれませんが。かつては、お母さんや家族がもっている業みたいなものもを赤ちゃんが一緒に流していってくれるという意味もあったそうです。だから、その命には意味があると自然に感じられた。ところが、周囲がそう関わらなくなって、そういう意味が失われてしまいました。
最近は、出血や腹痛など何の徴候もないのに、超音波検査で流産が簡単に診断されるようになりました。そして、診断されると、早めに掻爬手術をしてしまう傾向にあります。
手術の前に、赤ちゃんがそこに来ていること、来てくれた意味を感じてもらえるかかわりがあるといいんだけど・・・
流産の場合でも、そのまま見守っていればて、赤ちゃんはいい時期に産まれきてくれるんです。流産であっても、いいタイミングで陣痛を起こしてくれているように思います。
でも、そのためには情緒的サポートの体制がととのっていないとうまくないのですが・・・
今は難しいですよね。
ひとりめの出産を担当させてもらった方で、その後、子どもができず、不妊治療も引き続きさせてもらった方が、「先生、妊娠反応がでました」と受診されました。
「良かったね!」と私も喜び、超音波検査をしました。ところが、子宮の中には胎嚢という袋はあったのですが、小さく、すでに形もくずれていていました。
流産だろうと思いましたが、それまでの、彼女の時間を知っている僕は、その時にはそうは言えず、赤ちゃんが来てくれたことに、「おめでとう」って言葉が自然にでてきました。
その後の超音波検査で赤ちゃんが見えてくることはありませんでした。
その後、「とても辛い体験でしたが、先生に第2子の妊娠を喜んでいただけたことは一生忘れません」と、いう手紙をお母さんからもらいました。僕もとても嬉しかった。
赤ちゃんが見えないというのは、赤ちゃんがいないのではなく超音波検査で見えなかったということです。妊娠反応が出たということは、受精卵は子宮の中にたどりついて着床をしています。
飛行機から見たら、私たちひとりひとりの人間も見えなくても、私たちはここにいるように、超音波見えなくても、赤ちゃんはそこにたしかに来てくれているのです。
そして、お母さんの中で、命を全うしている。その目では見えない命を心で見る。
そういう意識が広がると違うんだけどな~って、いつも思っています。
医療の現場には、「問診票」というものがあります。
その人に会う前に、ある程度、その人の情報を把握するということは、とても大切なことです。でも妊娠されたと受診しても、その方が独身とか、過去に何回が中絶の既往が何回かあると書かれていれば、この方は今回も産まないのかな・・という感覚で、その方に接っしてしまうでしょう。
妊娠と診断した時、「おめでとう」っていっていいんだろうかと、考えてしまうわけです。
それはそれで悪くはないのかもしれません、ただ、医療の現場の中にいると、無意識のうちにその命の価値を決めている気がしてならないのです。望まれた授かった命と、望まれない妊娠、中絶となる命。社会的背景は違っていても、命としては優劣はないはずです。どういう状況でも、命が来てくれたことに対して「おめでとう」って素直に言えることは、命とかかわる「産科」スタッフには、とても大切ことではないのだどうかと、僕は思います。
伝え方やその後のかかわりも大きいのですが、結果的に中絶になっても、来てくれた命に「おめでとう」って言える接し方は大切ではないかと思うのです。
あなたもあなたのままでいられるケア
私たちのケアが、相手にとって良かったのかは、その時には分かりません。でも、5年後、10年後に、その方にとって、生きる糧となっている可能性もあるのです。
予期せぬ出来事に直面したときに、医学的に適切な対応をとることのほか、できるだけ、母親と家族があるがままでいれる環境をつくって、見守ってあげてほしいな、と思います。
その方がその方でいれるケアとは、自分たちも、あるがまままの私たちを意識する時間にもなるでしょう。あなたは、どのような状況だと、あなたのままでいれそうですか?
僕の場合は、相手が、周囲が、自分のことを否定しないで受容してくれる環境です。否定しないということは、相手の全てを肯定することではありません。ありのままの相手を受け入れてくれ、相手のあり方を尊重してくれる環境です。
そう考えていくと、その人を尊重できるケアができるようになるには、自分の生き方やあり方とつながっているのことがわかります。「あなたもあなたのままでいられるケア」が、これからの時代は、ますます求められていくと思いますが。
そのためにはは、自分って?ということから始めなくてはならない。
ケアをする側の、医療者の心の崩壊が起こってきています。それが産科の崩壊や、医療崩壊につながっています。表面的には、様々な対策や取り組みが行われていますが、それがなかなかうまくはいかないのは、組織やシステムだけで対応しようとしているからでしょう。実際に末端で関わっている個のあり方があまり尊重されていないからだと思います。
人と人が関わるあらゆる領域は、個と個の関係をいかに築けるのかにつきると思います。妊娠・出産・育児・恋愛・SEX・そして生と死。人が生きて行くってそういうことなのではないでしょうか。
そう意味で、これまでの医療モデルでは対応できなかった、個の問題に対し、自分たちがどう関わってゆくのだろうかというところが、今後、より問われてくるのでしょう。
自分たちがかかわる時間では物ごとは完結などしない。でも、それでも、その一瞬、一瞬が大切なんだということを知っておいてほしいです。日々それぞれが、あなた自身に素直に向き合い、今、自分で感じていることを、大切にしながら、それぞれの場でそれぞれができる一歩を踏み出していって欲しいと思います。