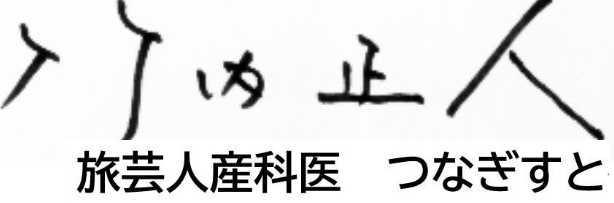NOTE ノート
今後の周産期医療システムの方向性~つなぐ"人間的モデルへの抜本的変革を~ 2011.3
はじめに
2000年代後半、わが国は産科医療危機と呼ばれる状況に直面し、周産期医療は社会でも広く関心と注目を集め、周産期医療システムについては、議論が繰り返されてきた。幸い、国を挙げての精力的な対応は一応の功を奏し、現在、当面の危機を乗り越え、周産期医療提供体制は徐々に整備されてきている。とくに、日本産婦人科学会を中心に、産婦人科医の待遇改善や医療体制の再構築を国や地方自治体に強く訴えかけたことなどにより、診療報酬改定や、ハイリスクの妊娠分娩加算、妊婦健診の公的助成は拡大され、実際に産婦人科医(とくに勤務医)の経済的な待遇も改善されており、出産に関わる医師の数は増えてきている。個々の制度には問題も含まれているが、パッケージとして考えると、この5年間の関係者の取り組みには深く敬意を表する。
ただし、全体的には日本の周産期医療はどこをめざしていくのかという本質的なコンセプトに切り込むことがないまま、より安心で安全な周産期医療を、全国にあまねく提供できるためにと動いているようにも見えてしまう。現在の一時的な安定は、のっぴきならない状況で、国の財政投入を含めた緊急避難的なアメ対策が与えられ続けてきた結果であり、いわば産婦人科バブルと考えてもいい。財政を考えてもこの施策が継続していくとは考えられず、いずれ梯子ははずされると考えたほうがよい。
システムの方向性を考えていくにあたり、最も大切なことは、一時的ではあったとしても、危機を超えつつある今だからこそ、日本の周産期医療には今後何が求められ、どこへ向かって進んでいくのか、今後の妊娠・出産の場と、周産期を担う施設や医療者の役割は何なのかを、私たち(医療者だけでなく、社会全体を含めた私たち)が再認識し、社会全体で共有していくことではないだろうか。今回の特集では、ここまで出産からみる社会状況、周産期医療の現状と課題、助産師の専門性、助産師がやるべきことなどを探ってきた。本稿では、システムの方向性もそうであるが、そのシステムの土台となる、これからの周産期医療がめざしていく“あり様”について、私見とはなるが、これまでの周産期医療の歩みを振り返り、今後の長期的な展望までを意識したうえで、少し大局的な視点で考えてみたい。
Ⅰ.産科医療危機のきっかけであった大野事件
1927(昭和2)年、関東大震災後の震災手形発行で、銀行の経営状態が悪化していた状況で、当時の片岡大蔵大臣が、国会の衆議院予算委員会で、まだ潰れていないのに「東京渡辺銀行が破綻」と失言したことがきっかけとなり、全国で銀行取付けが拡がり、多くの有力銀行が休業、破産し、関連企業の連鎖倒産も相次ぎ、昭和金融恐慌が起こった。こうした突発的な社会危機の勃発には、その以前に背景となる状況があり、そこへきっかけとなる出来事が起こる場合が多い。
今回の産科医療危機の直接のきっかけは2006年の福島県大野病院事件だろう。医師側の観点からは、過酷な労働条件による勤務医の疲弊、良いとは言えない病院の待遇、勤務医の開業医との待遇の不平等感、医師の都市部集中による医師数偏在と地域格差、他科と比較して医療訴訟が多いこと、社会から正当に評価されていると感じられない自尊心の低下、将来に対しての希望が持ちにくい閉塞感などの背景があって起こった出来事だ。
2005年、大野病院で前置胎盤による帝王切開を受けた産婦が、出血多量で産後に亡くなった。そして、翌2006年に担当医が起訴されることになる。当時、大野病院の産婦人科は起訴された担当医が1人常勤でお産を守っていた。しかし、この事件がきっかけとなり、1人医師の多くの産婦人科からは医師が引き上げられ、産婦人科が閉鎖された。あるいは、医師の引き上げはなかったものの、1人医師では、お産を取り扱わなくなっていった。
2002年前後から、医療事故が警察の捜査の対象とされ、医療者が犯罪の被疑者として扱われるケースが多くなり、メディアの報道もあいまって医療不信が増大し、医療安全に対する社会的要求が過度な高まりを見せていた。こうした社会的状況で、病院勤務の現場の医師の間では、リスクの大きい病院の勤務医を辞めてより負担の少ない病院へ移ったり、開業医になったりする、小松秀樹が言うところの「立ち去り型サボタージュ」1)と呼ばれる動きが、大野事件を契機に産婦人科で一層加速した。おりしも医学部卒業後の臨床研修制度の変更によって、2004~2005年は大学医局に医師が入局しない空白の2年間と呼ばれ、2006年は各大学産婦人科医局とも、新入医局員の確保ができなければ、医局の存続にもかかわる状況であった。そのタイミングで大野病院事件が起こったことで、学生にも産婦人科を敬遠する傾向が顕著に見られたのは、全国への医師の供給元であった医局にとって、あまりにも大きな痛手となった。
Ⅱ.産科医療危機は医療モデルの限界の反映か
私は当時この起訴を、患者(社会)と医療者(医療)の対立の極みととらえていた。そして、妊娠・出産を、やはり医療モデルだけで見ていくことに決定的な限界を感じていた。症状、徴候を原因、病理との関係で捉える医療モデルは、対象をできうるかぎり細分化して、周囲からの影響を排除しながら標準化し、エビデンスを見出していくあり方である。胎児を見ていくうえでは、胎児全体を臓器に分け、臓器を細胞に、細胞を染色体、遺伝子へとマクロからミクロへと展開していくことによって、周産期領域でも重要な新知見が発見され、現在の周産期管理が構築されていく基本となったあり方である。その医療モデルのキーワードは分離である。かつての、家族の入れなかった分娩室、分娩直後の母子分離、母子別室、3時間ごとの授乳など、医療モデル仕様の、妊婦を取り囲む環境はなくなっていき、立会い出産、カンガルーケア、母子同室、自律授乳といった、“つなぐ”をキーワードとした人間的モデルや助産モデルが、それに置き換わってきてはいるが、多くの医療者の、妊婦と家族への対応や、周産期のシステムは依然として医療モデル的なあり方が続いている。
Ⅲ.善意の周産期医療とは
妊娠・出産を支える医療者が善意で、妊産婦と家族を支えているのを前提とすれば、たとえ望んだとおりの幸せな結果ではなかったとしても、患者と医療者は本来、終局的には対立関係にはならないはずである。それは、命を支えてきたものは、その命を授かった家族とともに、不幸をともに悲しむ存在であるからである。しかし、医療モデルが進むと、医療者と患者の関係は変容していき、予期せぬ結果をともに悲しむことができなくなるようである。医学的な原因究明(検証)は、大切で欠かせない作業であるが、もし、この作業が私たち医療者から、患者家族とともに悲しむ感情を妨げ、無意識のうちに自らを正当化し、組織を守る風潮をつくっていったとすればどうだろう。これは善意の周産期医療と呼べるのだろうか。患者と医療者は歩み寄れるのだろうか。
医療過誤があった場合はどうであろう。その時点で良かれと考えて行ったことが、結果として過誤として見なされることもあるだろう。その場合は、正直に話して、説明するだけでなく、やはりともに悲しむことで、最後には許してもらうしかないのだと思う。裁判で勝っても、決して嬉しいわけではないだろう。勝者と敗者が法的判断を期にノーサイドになるわけでもなく、お互いの気持ちが癒されるというわけでもない。周産期における過誤の場合、その解決は、家族の気持ちが表出できたうえでの示談が前提となるべきである。不幸な結末であっても、その命が不当にとり扱われることがなくなれば、そのプロセスは、患者にとって救いになるだけでなく、医療者にとっても後への豊かな周産期医療へとつながりうる。これが命を扱う、家族と母子に寄り添う周産期医療の基本だと思う。
信頼性の欠如から周産期のケースが民事訴訟になるのさえどうかと思うが、もし善意の医療者を社会が刑事罰に処することがまかり通るのであれば、周産期医療は成立しなくなる。大野事件では、それがまかり通ってしまったのである。私の知る限りにおいて担当医の医療対応は適切であった。そして、社会的な注目を集めた結審でも医師は無罪となった。今後、司法が医療者を刑事罰に処する敷居は高くなったであろう。それでも、患者と医療者の向き合い方と、根本の意識がかわっていかなければ、周産期医療の将来への閉塞感を払拭していくこと難しいと思う。大野病院の家族への対応は不備もあったと思う。分離型で防衛的な対応もあったようだ。お母さんが亡くなっている。家族の不審感はどれほどのものだったのか推し量ることはできない。それでも、周産期医療が将来への希望を感じることができるあり方とは、どんな結果であろうとも、そんな状況に陥ろうとも、患者と医療者が同じ方向を見ることができる、対立のない関係性をつくれるあり方となろう。
そんなあり方を意識して、その根底に支えられる周産期システムをつくっていくべきである。
Ⅳ.周産期に求められる役割とは
次に、妊娠・出産の場、周産期に関わる医療(者)の役割について考えてみよう。まずは、産む女性の視点から見た、日本のお産文化の変遷を、第2次大戦後から簡単に振り返ってみよう。
1945年、米国のGHQ(連合軍司令部)の出産の医療化、施設化の方針がきっかけとなり、正常出産が自宅から施設で医療者の介助によって行われるようになっていったが、お産は文化である。方針がすぐに根づいたわけではなく、その傾向が本格化したのは、高度成長の時代に入った、1950~60年代からであった。病院出産は高度成長、富裕の象徴でもあったからである。その後、地域での重層的な人間関係、親戚、家族との関係が希薄化していく1970年代には、成人や結婚など、次なる段階への新しい意味を付与する、通過儀礼としての妊娠・出産のコンセプト、娘から母になる妊婦周囲の環境や関係性はなくなっていった。女性が慣習から解放され、個が尊重される時代の到来でもある。ラマーズ法が普及し、「反医療」と「自然なお産への回帰」の運動が拡がり、フレデリック・ルボワイエの「暴力なき出産」のアプローチから、「赤ちゃんが生まれる環境」という概念が紹介されたのもこの頃である。お産が通過儀礼から、私的な出来事となったという意味で、1970年代は日本におけるお産文化の大きな転機であった。
1980年代後半、バブル期に入ると、産み方からアメニティーへと関心が移ったが、バブル崩壊後の1990年代には、再び「人間的な出産」を取り戻そうという動きが活発化し、1994年には第1回「いいお産の日」が開催された。グローバリゼーションが進行し、英国人ジャネット・バラスカスのアクティブバースなどの考えが世界からも取り入れられ、自分たちで、産み場所や産み方を選択するんだという気運が生まれてきた。ところが、21世紀に入り、医療側が崩れだし、産科崩壊、産院閉鎖、出産難民などの現象が起こってくる。現在の混迷の世相は、これまでの流れから見れば、お産も自然回帰が唱えられる時代であろう。ところが、妊婦の高齢化、少子化も関係しているのか、医療を信頼しているとは思えない女性たちもが、玉石混交の情報に溺れ、不安の渦にのまれ、自分の身体、産む(潜在)力を信じることができず、医療に依存せざるをえないでいるように思える。お産文化の視点からは、1970年代に社会が崩れていき、個の時代に入ったが、今は産む個である女性とそれを支えるパートナーと家族の、人間力喪失の時代に入ってきているのではないだろうか。
人間力喪失の前の時代であれば、言葉は悪いが、どんなお産であったとしても、どんな周産期医療を提供されたとしても、お母さんと子どもが元気で(死なないで)病院を出ていければ、母と子、家族を受け入れて、支える地域・家族・親戚関係があったのである。ところが、今では、退院後の母子の受け皿が期待できなくなってしまっている。さらに言えば、将来的に期待できるようになるとも思えない。かつてはお産が一応のゴールでよくても、今後はそうはならないということである。問題を抱えた母子を保健所や児童相談所など任せにする状況は、物理的に到底困難となるばかりでなく、社会的に問題のありそうな女性・家族を、切り捨てざるをえない世知がない周産期医療が展開されていけば、患者(社会)と医療者(医療)の関係性も増悪していき、再度の崩壊危機を迎えることであろう。
“人(新生児)は独りでは生きていけない”ということを、周産期医療は改めて意識しなければならない。新しい命が健全に育まれていくために、妊娠・出産での関わりをも含めた周産期医療は、医師、助産師、看護師の枠を超えて、女性が母になるプロセスを支える、かつての地域や家族の役割まで担っていく覚悟を持つ時代に差しかかっている。大変そう? 無理ではないのか? と感じるかもしれないが、私たちがこの意識を持って働けることで、周産期医療に携わる個々のモチベーションと、周産期を選択する者の志は高まり、医療者と社会(家族)の関係性、信頼感も大きく改善し、周産期医療に光明が差してくると思う。周産期医療は自律し、そこで完結するのではなく、社会と生活の中にある、次へとつないでいく医療である。
Ⅴ.新生児医療の発展と産科医療の変容
これまで周産期医療と書いてきたことは、主として産科の視点であるが、周産期の中の産科の立ち位置は、周産期医療が発展していくにつれて大きく変わってきた。一般に周産期医療の発展という場合、世界的に見て新生児医療の発展を指す。たとえば、国際母子保健の世界では、途上国に周産期医療が介入することで、妊産婦死亡はそれほど変化ないが、周産期死亡や乳幼児死亡は激減することがわかっている。日本の周産期医療でも、産科医療と比較すると、新生児医療のほうがより技術的にもケアという質的にも発展してきていて、新生児医療の進歩が産科医療の質も変容させてきた。たとえば、ここ20年で妊娠高血圧症候群や、前期破水など妊娠中に何らかのトラブルがあった場合の児の娩出時期が大きく変わってきている。以前であれば、降圧剤、抗生物質、子宮収縮抑制剤などを利用して、妊娠期間をいかに延ばし、可能であればタイミングをみて経膣分娩に持っていくのが産科管理の妙であったが、最近は新生児管理が可能な時期であれば、速やかに帝王切開でターミネーションをし、赤ちゃんを新生児医療側へと手渡すのが一般的となった。かつては、入院期間中に妊婦や家族の不安とも向き合える時間と環境があったが、極端に言えば、産科は児を娩出するために通り過ぎるだけの場となり、“関わる”ケアの部分がなくなっていった。その代わりに、胎児診断などで、できうるかぎり早い時期に異常のある児を発見することに勢力が注がれるようになった。
一方、新生児医療は21世紀に入り医療モデルだけでなく、つなぐ人間的モデルも尊重するようになってきた。その象徴の一つがディベロプメンタルケアである。“助ける”視点からは、生育限界にまで到達した新生児医療は、障害なき生存(intact survival)から、さらに医学生物学的評価を超えていこうとしている。
堀内2)らは、「親が親になるには妊娠・出産・産褥期に母子が相互的に影響を及ぼし合いながら、父親も巻き込んで発達するものであることもわかってきた。一般的な医療環境とは異なったいわば発育発達する生活環境について考慮し生活環境について考慮し、親子のミクロ環境を調節することが新生児医療の大切な部分となりつつある。そうした取り組みの一部をdevelopmental careと呼んでいる」と、述べている。新生児医療では、NICU退院後の長期的なフォローアップの充実が、発育・発達に影響を及ぼす児の周辺環境までの総合的な評価を現場にフィードバックしていることが大きいのだろう。
Ⅵ.1次医療を中心にして周産期システムを組む
総論が長くなったが、産科あっても、安心・安全な出産を超えて、将来の家族の生活まで意識できる家族のディベロプメンタルケア、まさに今後の産科に求められている役割であろう。そう意識できることで、患者(社会)との関係性は改善し、医療者のモチベーションも向上し、維持できる。そして、こうしたあり方を支えるのが1次医療である。新生児科医の堀内3)は、「医療には診断、選択、技術提供のような父性的な切り裂き、決断していく側面と、そうした事態を包み込むように全体的に見守り、支援するケアといわれる母性的なものとが調和して、初めてバランスが取れるものだと私は理解しています。周産期の取り組みには医療ももちろん不可欠ですが、広範な母子ケアがそのバックボーンとしてあるのは皆さん納得することだと思います。しかし、今の、我が国の現状は周産期医療の父性的な面だけが強調されすぎて、母性的なものを非合理と切り捨てる傾向があるように思います」と、述べているが、筆者もまさに同感である。
世界最善の周産期指標となった日本だが、短期指標の改善は必ずしも、母子、家族、社会の幸福を意味していなかった。政治、経済、教育、福祉も、わが国の将来は決して明るくない。そんな状況で、産科医療危機が起こったことを忘れてはならない。「産婦人科医療改革グランドデザイン」といった骨太の考え方も提示されてきているが、これまでの延長線上で周産期を捉え、その上にシステムを構築していこうとすれば、いずれは再度の危機、さらには本格的な崩壊を迎える可能性が高くなるだろう。だからこそ、今後はシステムを構築していくうえでも、これまで切り捨ててきた母性的な感覚を取り入れ、“つなぐ”人間的モデルを意識した、抜本的な変革が必要となってくる。具体的には、現在はどちらかといえば、高次施設ありきで対策が進んでいるが、その反対に、地域の1次医療を中心に周産期医療システムを構築していくことを提案したい。1次医療が魅力ある場であってこそ、高次医療も活性化し、医療者間の関係性も向上し、周産期システムは循環していくという考えである。今の、産科医療、周産期医療の停滞は1次施設の役割が軽視されてきたからであろう。
産む・産まれる場である1次施設が、地域で孤立するのでなく、それぞれの地域の状況に応じて、役所、役場、保健所、学校、地域のコミュニティーなど、生活の場と広くつながることで、産まれたら終わりでなく、出産後の母子と家族と長く関われる場、昔の寺のような役目が担えるクリエイティブな場になることをめざしていくのがいい。医学部や看護学部、助産課程終了後は高次施設でトレーニングを積むが、周産期の究極の醍醐味は人と関わることである。高次施設を経験した多くの者が、地域(1次医療)での勤務を希望するような魅力ある1次施設が、日本各地で数多く出てくることが、1次、2次、3次にかかわらず、周産期医療を、周産期に携わるスタッフ、そして、そんなスタッフに支えられ周産期を過ごす女性と家族のあり様を変化させていくだろう。
おわりに
最近、友人と話していて、妙に納得したというか、危惧したことがある。日本では、近い将来、子どもは自分で産むのでも、産ませてもらうのでもなく、他人に産んでもらう時代が来るのではないかというのである。「結婚したいとは思わないし、“この男”の子を産みたいってこともない。でも、もう40だし子どもは欲しい。ただ、お産は痛いし、恐いし、自分で産む自信はない。帝王切開になれば傷が残るし、死にたくもない。妊娠すれば好きなことができなくなるし、仕事は続けられなくなって、経済的にも損だし、キャリアも中断しちゃう。自分で産む意味がどこにあるの? 母もそう言っている。バンクで精子をもらって、顕微授精して凍らせてインドに送ればいいんでしょ。インドの女性たちだって子宮を貸すことで豊かになれるんだから…」
産む、産まないは個人の自由であるし、皆が産めるわけでもない。それでも、漠然とでもいいから、産みたいなと思えうるような1次施設が、各地に生まれてくる。そこで働く医療者は大変であっても、やりがいがあって、生き生きと働いている。そんな医療者を見た次世代が、また周産期の場で働きたいと思う。そんな1次施設をサポートするような試みが、高次施設も含めた、周産期医療とシステムを支えていく一番の方策であると考える。
文 献
1)小松秀樹:医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か、朝日新聞社、2006
2)堀内勁、相亰美穂、笹本優佳:新生児 Developmental Care、周産期医学、36(増 刊);855-857、2006
3)堀内勁:私信による、2010
Nurse eye24巻1号 Page50-57(2011.03)